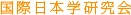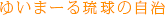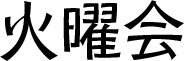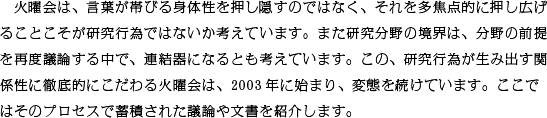火曜会(第41期)の予定
既に終了しています。
火曜会
2024年春
第41期
2024年4月24日
冨山一郎
Ⅰなぜ集まるのか
鶴見俊輔が同志社に来たことを契機に始まったサークルに、1963年にはじまった「家の会」というものがあります。ここでは、家というテーマというより、サークルという集まり、あるいは集まるということをそこから考えてみたいと思います。この「家の会」は家にかかわる問題を記録し考える場ですが、鶴見は家を「無意識の習慣」とよび「無意識の部分とある程度、向き合うようなことがなければ、どうしてわれわれは〝自分の思想を持つ〟などといえるのか、それが結局、家の会のテーマでしょう」と述べています。
自らの思考や知識にこうした「無意識の習慣」を持たない人はいません。思想にせよ知識にせよ、たんに本読んで覚える行為ではないのです。いや、覚えるということ自体、この「無意識の習慣」と切り離せるはずはありません。そして問題はここで鶴見がいう「向き合う」というのはどういうことなのかということです。続けて鶴見は次のようにも述べています。
無意識の習慣として続けていけば非常に強固につづくものを、百足がどういうふうにして歩くのかと考えたら歩けなくなった、という話があるのだけれども、そういう違和感が生じて、かえって家というものの円満な交通というものが妨げられるということがありますね。だから、われわれが無意識としてしまっておけばよいものをしまっておかないことによって、平地に波乱を起こすということが確かにあると思うですよ。
「違和感」や「波乱」が、「自分の思想を持つ」ということにつながるのだと鶴見はいっているのです。トラブルこそが知であり、思想であり「向き合う」ことの始まりなのです。考えなければよかったのに、考えると歩けなくなる。歩けなくなることこそが考えるということなのかもしれません。ここで鶴見のいう「平地」に少しこだわっておきたいと思います。
「平地」で生きることが自然だと感じることがあるとして、でもそう思えない人もいるでしょう。すなわち「平地」がある者たちにとっては強要された生であることもあるでしょう。そこでは「平地」は自然物でもなんでもなく、抑圧機構に他なりません。そしてその抑圧はある人にとっては自然であり、鶴見のいい方を借りれば無意識の底にしまっておいても全く普通でいられるのです。ですがそうではない場合はどうでしょうか。そこに知や思想、すなわち「向き合う」ことの始まりがあります。ではその「平地」をどう語るのか。例えばスピヴァクは家父長制について次のように述べています。
私は『家父長制』―父の支配―という語を使用しない。なぜならそれは生物学的であり、自然主義的であり、そして/あるいは歴史実証的な解釈からの影響を受けやすいからであり、もっともしばしば私たちに非難の場以外の何者でもない場を供給する他ないからである。(ガヤトリ・C・スピヴァク「置き換えと女性の言説」長原豊訳『現代思想』vol.25-13、1997年、195頁)
スピヴァクは非難をすることが無用だといっているのではありません。しかしそれ以外の場もあるといっているのです。また『タッチング・フィーリング』でイブ・コソフスキー・セジウイックがいう「パラノイア的読解」ということを展開していますが、セジウイックは「パラノイアは暴露に信頼を寄せる」(221)と述べ、敵を明確に据えることにより生き延びようとする戦術が確かにあるとまず述べています。すなわち自然化された「平地」が実は構築された抑圧であることを暴露することは、やはり必要なのです。しかしそこには二つの問題が抱え込まれています。
一つは、偽りの暴露の先に顕在化が予定される真の姿という真実性への呪縛であり、また二つ目は、逆に抑圧が動かしがたい自然として現前に浮かび上がる時に生じる無力感です。そしてこの無力感は、真実の姿を希求し防衛しようとする呪縛の燃料にもなるでしょう。こうしたパラノイア的読解が仮に集団を作り上げるとするなら、真実の姿を持たない、あるいは持てない者たちを周縁に追いやり、場合のよってはその存在すら否定する権力になるかもしれません。
またそれは知の在り方とも深く結びついています。同書を翻訳した岸まどかさんがいうように、「じゅうぶん賢くさえあれば、じゅうぶんに意識的でさえあれば、見えない権力の隠微な支配にからめとられることなくあの痛み(自分のものであれ他人のものであれ)回避できたんじゃないかと願う心が理論武装の内側にある」(「訳者解説」339)わけです。こうして真実性の権力は理論化され、普遍化されてしまします。こうなると議論はどちらがマウントをとるかに転化していきますが、岸さんは「その甲冑のひもを緩めるのは簡単ではない」といいます。スピヴァクが拒否し、またセジウイックが「パラノイア的読解」として批判するのは、この権力なのでしょう。
では別の場とは。セジウイックが「パラノイア的読解」に対して「修復的読解」と述べる語り口とは、あえていえば関係性を新たに作り直していく実践であり、可能性を自らに関係することとして拾い集め、新たな関係を確保する言葉として語りなおしていく作業です。この作業について中井亜佐子さんは「あらたに全体性を作り出そうとする動きであり、つねに未完のまま終わるプロセスである」(中井亜佐子『エドワード・サイード ある批評家の残響』193)と述べていますが、そこでは「未完のまま終わるプロセス」にとどまり続けることが重要だと思います。
そしてこうした意味において鶴見は、重要な点を指摘しているといえるでしょう。すなわち「平地」は暴露する対象ではなく、そこに生きる者として波乱をみいだし、混乱しながら、丁寧にそれを拾い集め、関係性を作り上げていく作業の始まりとしてあります。そして平地には、この始まりをおこなう場をつくること。そこには真実性というより、それぞれの波乱や混乱、躓きがありますが、平地ではありえなかった関係性や他者との出会いがたえず生じます。その関係性や出会いを事後的に場とよんでおけばいいのでしょう。ですから参加には何の制約もありません。まずは参加すること。
Ⅱ進め方について
1火曜会の構造
火曜会の場は、三重の構造になっています。まずメーリングリストにおいて表現される場 ですが、これ火曜会で議論をした経験を持つ人々において構成されています。人数は 100 名 を超え、また東アジアや北米だけではなく、ヨーロッパ、北欧、北アフリカにまでひろがっています。こうしたメーリングリストの広がりの中で、定期的な火曜会が開かれています。
またそうであるがゆえに、時々、「「言葉を置く」ためにやってくる旅人のような存在」(西川さんの「火曜会通 信」89 号 http://doshisha-aor.net/place/619/)として、登場する人々がいるのです。これが二つ目の領域。流動する旅人の領域です
最後が直接対面で行われる火曜会です。こうした三重構造(旅人は構造というより流動系ですが)になっています。
また火曜会は「演習Ⅰ、Ⅱ」「現代アジア特殊研究」でもありますが、さらに対外的に使 える形式として次の三つがあります。一つは、火曜会を同志社大学<奄美―沖縄―琉球>研究センターによる「定例研究会」の通称としても使えるようにしています。今期でしたら定例研究会(第 41期)としたいと思います。研究センターの定例研究会、通称「火曜会」です。
もちろんこのような名称を用いるかどうかは、自由です。基本的には「火曜会」は「火曜会」なのであり、カリキュラム上の科目でもなく、「定例研究会」でもありません。ただ擬 態を用意しておこうという訳です。
2すすめ方
事前に文章を読んできた後、一人ひとり順に注釈やコメントを話すようにしています。こ のやり方において見えてきたのは、言葉が堆積していく面白さです。しかもその言葉たちが、 順に回すという力によってなされているので、しばしば「無理にでも」話そうとするという 性格を帯びるため、ある種の受動性が能動性に転化していくような出発点を一人一人の言 葉が担っているような感触もあります。すべての参加者の「私」が出発点になっているので す。こんな言葉が、私たちの前の空間に次から次へと降り積もっていくのが、面白いのです。
それはあたかも一人ひとりが参加してノミをふるい、批評し合いながら一つの彫刻を作り上げて いくような感覚です。火曜会ではディスカッション・ペーパーを前にした平等を前提に、一 人ひとりが報告者であり、彫刻者です。
ただ問題もあります。次の展開、すなわち一人ひとりが一通りコメントし終わった後の全 体として議論を進めるのに時間がかかるという問題です。この時間にかかわって二点提起 します。ひとつは一人ずつのコメントについて以前から「パス」ということを気軽にいおうということが提起されています。これは続けたいと思います。また最初の注釈やコメントを、最初の「読む時間」において各自できうる限り考えを準備しておくように心がけるというのもいいかもしれません。いま一つは、コメントの後の議論のすすめ方です。雪だるま式に積もっていくコメントを 議論にするのは大変です。またあせってすすめると多くの場合論点が見失われることがおきます。これをできるだけ防ぐのは一つには司会の役割ですが、司会だけではなく参加者が 目の前に堆積したコメント集合を丁寧に彫刻していくことが重要です。
3ディスカッション・ペーパーの配布について
ディスカッション・ペーパーは事前に配布します。前の週の土曜日までに MLで配布してください。また上に述べた火曜会の構造にもかかわりますが、配布をMLにかんして「誰が読んでいるのかわからない」「勝手に引用されたら」といった危惧があるかもしれません。ただ他方で、「議論の場に居合わせることがなくても、あるいは直接お会いすることはなくても、メーリングリストを通じて、既知の人、未知の人が、どこか別の時に、別の文脈で、このペーパーを読んでいるのかもしれない」(前述の西川さんの「火曜会通信」)というのは火曜会の広がりでもあり、またこのひろがりにおいて、先に述べた「「言葉を置く」ためにやってくる旅人のような存 在」が確保されているともいえます。まずはペーパーの無断引用厳禁ということを再確認しておきたいと思います。
4司会についてなど
第34期から司会を回り持ちにしています。今期も報告者が事前に司会者を指定すること にしたいと思います。司会をどのようにやるか、たとえば積極的にコーディネイトするかど うかは、司会者におまかせします。そのうえで司会については、上記の2の最後で述べ たように、コメントから議論へという展開をどうするのかということにおいて、少し意識的 に考えてほしいと思います。またそのためには司会になった人は、全体のコメントに注意を 向ける必要があります。
Ⅲ『火曜会通信』
火曜会にかかわる様々な文書は、http://doshisha-aor.net/place/644/に収められています。 火曜会が初めての人はぜひアクセスしてみてください。これまで火曜会で何をしてきたの かということがわかります。また『火曜会通信』というものがあり、それは火曜会での議論 をふまえた『通信』です。しばしば『通信』を楽しみにしているという声が届きます。それ は上記の火曜会の構造の第一の層にもかかわるでしょう。ですが、この間通信は出せていません。ぜひ執筆してください。文章は私のところへ送っていただければ掲載します。
Ⅳ雑誌『MFE』について
雑誌『多焦点拡張 MFE』https://sites.google.com/view/webmfe/
http://doshisha-aor.net/mfe/808/
創刊準備号を入れ4 号まででました。もうすぐ5号がでます。「MFE」は「多焦点的拡張主義(Multifokaler Expansionismus=MFE)」の略語です。この言葉は、1960 年代後半に西ドイツのハイデルベル ク大学医学部精神科の助手や患者を中心に生まれた社会主義患者同盟(Sozialistisches Patientenkollektiv=SPK)が遺した言葉で、それは、「精神病」が体現する禁止の領域を人々が集まる場所(暖炉)に変えていく運動を意味しています。また「焦点(fokus)」という言葉には、禁止と暖炉の二つの意味が重ねられています。さらにまたここでいう拡張、すなわち広がるということとは、同質な多数派を構成していくことではなく、自らの住まう既存の世界がその存立前提として禁止してきた領域を問い、禁止された領域とともに変わっていく運動としてあります。また焦点とは、このような既存の世界の前提を問う動態の中で見出される場なのです。
SPK については詳しくは冨山の『始まりの知』を読んでいただきたいのですが、ともあれ学の領域や区分にかかわる言葉ではなく、禁止を暖炉に作り変え続けていく運動 (expansionismus)を、雑誌名に掲げました。それは、雑誌『MFE』が担う、思考の場の新たな生成と連結が、既存の世界の前提を問い続ける運動になると、確信しているからに他なりません。こうした雑誌と運動について、「雑誌の「雑性」について」という題で『思想』2023 年 3 月号の「思想の言葉」で書きました。MFE についても言及しています。よければ読んでください。https://tanemaki.iwanami.co.jp/posts/7022
Ⅴ金曜の授業 3 限(13 時 10 分より)
「始まりとしての声」
Ⅵ予定
表題は仮です。報告者が再度アナウンスをしてください。
5/8 酒井朋子、奥田太郎、中村沙絵、福永真弓編著『汚穢のリズム』を読む
案内 内藤あゆき
5/15 新聞『家庭労働者』を読む(part 2)
報告 姜喜代
5/22 スナラウ・テーラー『荷を引く獣たち』(今津有梨訳)をめぐって
報告 山口詩央里
5/29 李恩子『日常から見る周縁性』を読む
案内 李真煕
6/5 沖縄戦における飢餓について
―移動する宇土部隊と住民飢餓―
報告 謝花直美
6/12 雑誌『少女座』を読む
報告 手嶋彩世子
6/19 声と児童文学の中/外の家族像
報告 日高由貴
6/26 1950年代から1960年代にかけての子供の保護と育成にかかわる社会的な動きから見る沖縄戦後史
報告 木谷彰宏
7/3 県外移設論をどう考えるか
報告 島袋琉
7/10 暴力の「後」を考える
報告 廣野量子
7/17 「できる」ということ、「できない」ということ
報告 沈正明
7/24 自分のこととして
―ハルモニの告白からー
報告 金大勲
7/31 二人の書道家の判事記録を読む
報告 やお