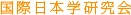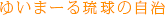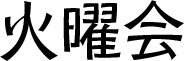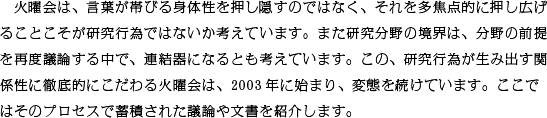火曜会(第42期)の予定
既に終了しています。
火曜会(第42期)
2024年秋
同志社大学烏丸キャンパス志高館SK214
15時より
2024年10月2日
冨山
Ⅰはじめに
知や知的営みは、私的所有や個人業績(量)において意味づけられるというよりも、また私的所有物としての知を前提にした社会のニーズや社会的影響、あるいは所有者(知識人)による啓蒙ということでもなく、知それ自体が他者との関係性や集団性にかかわる行為遂行的な営みではないか。火曜会は、こうした問いから始まりました。今期は42期ですから、単純計算すると21年続いてきたことになります。そこで書いたものを最近読み直しています。それは『始まりの知』を書いた時にも行った作業ですが、大学との付き合いもあと3年余りになってきたので、これからどうするかということを考えるための省察として、読み返しています。
火曜会を考える際に、この5年あまり美学者の中井正一のことをしばしば参照しています。中井は山代巴とともに農村の民主化運動にとりくむなかで、社会を変革する思想において重要なのは、「知識の多少、思想の寡多の問題ではなくして、契機と契機の構造」であると述べています(中井「農村の思想」1951年)。そこには誰かが指導者になって知識をあたえ、啓蒙することによって構成されるのではない集合性が、想定されています。それは、知の占有者による啓蒙ではなく、一人ひとりが契機となり連鎖してくようなそんな関係でありプロセスです。また先ほど「行為遂行的な営み」といいましたが、ようするにその営みとは、読む、聞く、話す、書くといった言葉をめぐる動詞の集合体のことです。こうした行為が「契機と契機の構造」につながるというわけです。
1936年に書かれた「委員会の論理」において中井は、ガブリエル・タルドの公衆論に言及しながら読むということは経験において読むことであると述べました。それはそれぞれの経験において読むことが、経験が言葉を持つということであり、読んだことを話すことあるいは書くことは、個別に見える経験が他者に読まれうる経験として登場することでもあり、それはまさしく経験を言葉において縁取るということなのでしょう。また聞くということも、こうした経験と言葉の間にあるといえるかもしれません。それぞれが契機となるということは、読む、聞く、話す、書くといった言葉にかかわる行為のプロセスの中で経験が言葉において縁どられていくことではないでしょうか。そこでは指導者による正しい知識の伝達を受け取るという受動性ではなく、受動性と能動性が入り混じっています。
後で述べるように、火曜会は多くの場合、事前に文章が配布され、読んできたうえで一人一人がそれについてコメントし、注釈を加えていくことから始まります。このコメントするというどこにでもある行為が、一つ一つの契機になるのであり、それは黙って聞いているということにおいてもすでに始まっているといえるでしょう。またそもそも経験はいつも言葉からはみ出し続けるのであり、そのうえで言葉において縁どるわけですから、黙って聞くあるいは言葉に詰まる、ただ眺めているということは、言葉の停止ではなく、経験が言葉を求める新たな始まりの瞬間です。またそれは既存の言葉の拒否でもあるでしょう。拒否は始まりでもあるのです。ですから話すことが見つからなくても、読んでこられなくても、話したくなくても、その場にいるということは、契機と契機が連鎖していく関係性においてはとても重要です。
ところで今「眺める」といいましたが、こうした言葉の世界との関係において、みるということの意味も浮かび上がるように思います。それは身振りや表情をみるということでもあるでしょうし、またそもそも映像をみるということにも関係します。映画を論じているレイ・チョウは、『プリミティヴへの情熱』で、「私が試みているのは、複数の媒体、複数の文化、そして複数の学問分野のあいだの書き換えとして、映画を理論化することである」と述べています。ここでいう理論化がどういうものなのかということは今少し置いておくとして、ここで注目したいのは、既存の区分や領域を「書き換え」ていくプロセスとして映画をみるということがあるという点です。
レイ・チョウさんは、さらに「視覚映像との出会いがどのような変化を引き起こしたか」という問いを立て、さらに「あらゆる視覚映像との出会いに関して肝心なことは、このどのようなという問いなのだ」と述べています。理論化とはこの問いを言葉にすることなのかもしれません。すなわちそれは映像との出会いの書記化であり、そこにもそれぞれの経験が引き出されているはずです。さらにその上でレイ・チョウさんは、書記化において重要なのは「絵がテキストになることではなく、言語テキストが絵に変化することだ」と述べています。新しい言葉の姿。中井は治安維持法で逮捕される直前に「集団は新たな言葉の姿を求めている」と記していますが、そこには視覚にかかわる言葉の姿も間違いなく含まれていると思います。映像をみたいですね。
Ⅱすすめかたについて
1火曜会の構造
火曜会の場は、三重の構造になっています。まずメーリングリストにおいて表現される場 ですが、これ火曜会で議論をした経験を持つ人々において構成されています。人数は 100 名 を超え、また東アジアや北米だけではなく、ヨーロッパ、北欧、北アフリカにまでひろがっています。こうしたメーリングリストの広がりの中で、定期的な火曜会が開かれています。またそうであるがゆえに、時々、「「言葉を置く」ためにやってくる旅人のような存在」(西川さんの「火曜会通 信」89 号 http://doshisha-aor.net/place/619/)として、登場する人々がいるのです。これが二つ目の領域。流動する旅人の領域です最後が直接対面で行われる火曜会です。こうした三重構造(旅人は構造というより流動系ですが)になっています。
また火曜会は「演習Ⅰ、Ⅱ」「現代アジア特殊研究」でもありますが、さらに対外的に使 える形式として次の三つがあります。一つは、火曜会を同志社大学<奄美―沖縄―琉球>研究センターによる「定例研究会」の通称としても使えるようにしています。今期でしたら定例研究会(第 41期)としたいと思います。研究センターの定例研究会、通称「火曜会」です。
もちろんこのような名称を用いるかどうかは、自由です。基本的には「火曜会」は「火曜会」なのであり、カリキュラム上の科目でもなく、「定例研究会」でもありません。ただ擬 態を用意しておこうという訳です。
2すすめかた
最初にも述べたように、事前に文章を読んできた後、一人ひとり順に注釈やコメントを話すようにしています。このやり方において見えてきたのは、言葉が堆積していく面白さです。それは最初に述べた契機と契機の連鎖といえるかもしれません。しかもその言葉たちが、 順に回すという力によってなされているので、しばしば「無理にでも」話そうとするという 性格を帯びるため、ある種の受動性が能動性に転化していくような出発点を一人一人の言葉が担っているような感触もあります。すべての参加者の「私」が出発点になっているので す。こんな言葉が、私たちの前の空間に次から次へと降り積もっていくのが、面白いのです。
それはあたかも一人ひとりが参加してノミをふるい、批評し合いながら一つの彫刻を作り上げていくような感覚です。火曜会ではディスカッション・ペーパーを前にした平等を前提に、一人ひとりが報告者であり、彫刻者です。
ただ問題もあります。次の展開、すなわち一人ひとりが一通りコメントし終わった後の全 体として議論を進めるのに時間がかかるという問題です。この時間にかかわって二点提起 します。ひとつは一人ずつのコメントについて以前から「パス」ということを気軽にいおうということが提起されています。この「パス」は、最初に述べたように、言葉が見つからないという重要な出発点でもあると思います。また最初の注釈やコメントを、最初の「読む時間」において各自できうる限り考えを準備しておくように心がけるというのもいいかもしれません。いま一つは、コメントの後の議論のすすめ方です。雪だるま式に積もっていくコメントを議論にもっていくのは大変です。またあせってすすめると多くの場合論点が見失われることがおきます。これをできるだけ防ぐのは一つには司会の役割ですが、司会だけではなく参加者が 目の前に堆積したコメント集合を丁寧に彫刻していくことが重要です。
3ディスカッション・ペーパーの配布について
ディスカッション・ペーパーは事前に配布します。前の週の土曜日までに MLで配布してください。またメモや箇条書きではなく短くても文章として作成してください。読むという行為をしっかりと確保しておきたいのです。
上に述べた火曜会の構造にもかかわりますが、配布をMLにかんして「誰が読んでいるのかわからない」「勝手に引用されたら」といった危惧があるかもしれません。ただ他方で、「議論の場に居合わせることがなくても、あるいは直接お会いすることはなくても、メーリングリストを通じて、既知の人、未知の人が、どこか別の時に、別の文脈で、このペーパーを読んでいるのかもしれない」(前述の西川さんの「火曜会通信」)というのは火曜会の広がりでもあり、またこのひろがりにおいて、先に述べた「「言葉を置く」ためにやってくる旅人のような存在」が確保されているともいえます。まずはペーパーの無断引用厳禁ということを再確認しておきたいと思います。
4司会についてなど
34期から司会を回り持ちにしています。今期も報告者が事前に司会者を指定することにしたいと思います。司会をどのようにやるか、たとえば積極的にコーディネイトするかど うかは、司会者におまかせします。そのうえで司会については、上記の2の最後で述べたように、コメントから議論へという展開をどうするのかということにおいて、少し意識的に考えてほしいと思います。またそのためには司会になった人は、全体のコメントに注意を向ける必要があります。
Ⅲ『火曜会通信』
火曜会にかかわる様々な文書は、http://doshisha-aor.net/place/644/に収められています。 火曜会が初めての人はぜひアクセスしてみてください。これまで火曜会で何をしてきたの かということがわかります。また『火曜会通信』というものがあり、それは火曜会での議論 をふまえた『通信』です。しばしば『通信』を楽しみにしているという声が届きます。それ は上記の火曜会の構造の第一の層にもかかわるでしょう。ですが、この間通信は出せていません。ぜひ執筆してください。文章は私のところへ送っていただければ掲載します。
Ⅳ雑誌『MFE』について
創刊準備号を入れ5号まででました。5号の特集は「留置と拘束」です。11月2日には『多焦点拡張』第5号の合評会があります。執筆した人はもちろん、しなかった人もぜひご参加ください。
5号については以下を見てください。
https://sites.google.com/view/webmfe/
http://doshisha-aor.net/mfe/808/
「MFE」は「多焦点的拡張主義(Multifokaler Expansionismus=MFE)」の略語です。この言葉は、1960 年代後半に西ドイツのハイデルベル ク大学医学部精神科の助手や患者を中心に生まれた社会主義患者同盟(Sozialistisches Patientenkollektiv=SPK)が遺した言葉で、それは、「精神病」が体現する禁止の領域を人々が集まる場所(暖炉)に変えていく運動を意味しています。また「焦点(fokus)」という言葉には、禁止と暖炉の二つの意味が重ねられています。さらにまたここでいう拡張、すなわち広がるということとは、同質な多数派を構成していくことではなく、自らの住まう既存の世界がその存立前提として禁止してきた領域を問い、禁止された領域とともに変わっていく運動としてあります。また焦点とは、このような既存の世界の前提を問う動態の中で見出される場なのです。
SPK については詳しくは冨山の『始まりの知』を読んでいただきたいのですが、ともあれ学の領域や区分にかかわる言葉ではなく、禁止を暖炉に作り変え続けていく運動 (expansionismus)を、雑誌名に掲げました。それは、雑誌『MFE』が担う、思考の場の新たな生成と連結が、既存の世界の前提を問い続ける運動になると、確信しているからに他なりません。こうした雑誌と運動について、「雑誌の「雑性」について」という題で『思想』2023 年 3 月号の「思想の言葉」で書きました。MFE についても言及しています。よければ読んでください。https://tanemaki.iwanami.co.jp/posts/7022
Ⅴ金曜の授業(SK214)
◆2限(10時45分より)
マンガを読みます。マンガ論を読み、今日マチ子を読み、それぞれの推しについても話すことになります。
◆3限(13時10分より)
目取真俊、又吉栄喜、崎山多美を読みます
参加を希望される方は、ご連絡ください。今週からです。
Ⅵその他
12月21日(土曜)13時より、同志社人文科学研究所創立80周年記念シンポがあります。私が基調講演をするのですが(「共に考えるということ―知と集団をめぐる省察―」)、火曜会について話そうと思っています。よければ聞きに来てください。
Ⅵ予定
表題は仮のものです。期日が近づいたら各自アナウンスをしてください。
10/9 ダラ・コスタにあいに行く
フィールド・ワーク報告 姜喜代
10/16 休み(中間報告会のため)
10/23 開高健『最後の晩餐』をめぐって
報告 内藤あゆき
10/30 自生的秩序における予見不可能性について
報告 島袋琉
11/6 未定
11/13 二人の書道家の判事記録を読む
報告 姚一鳴
11/21 暴力の「後」を生きる
報告 廣野量子
11/27 休み(創立記念行事のため)
12/4 映画を見ます
12/11 これからもダラ・コスタとともに
報告 姜喜代
12/18 無名の人の語りに寄り添う
―ライフヒストリーから考えるー
報告 寺田真千
1/8 三島由紀夫における「伝統」と「自己愛」
報告 李啓三
1/15 流れ出る人々と故郷
報告 李真煕
1/22 「獣のはらわた」(アメリカ帝国内の中)から抗う女性
報告 金美穂
このあと、打ち上げパーティーをします