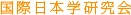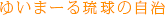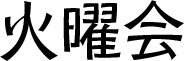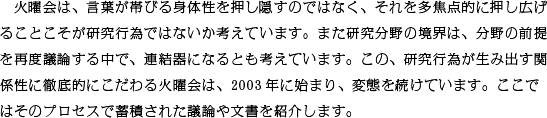火曜会通信(100)
先日(2025年5月31日)おこなわれた、ドキュメンタリー『やさしく』の上映会とトークイベントへの米田量さんからのメッセージです。
*****
火曜会のみなさま
上映会に関わられたみなさま
上映会、意義の深い企画の開催を大変ありがとうございました。
自分が何かの映画を観るにあたって、一人で映画館に行ったり、自宅で鑑賞するだけになるのと、すこしであっても関わりある方、そこに何かを感じる方とともに映画を観て、そこからひきおこされたものが互いに伝えてもらえることで、得られること、受ける影響がまるで違うなとあらためて思いました。
それぞれの人が、映画のどこにそれぞれの内在的なプロセス、あるいは経験を触発されたのかということ、加えて自分が自覚できないことを別の人が自覚し経験することを介して、その経験が自分という殻の自覚のない遮断をこえて浸透してきてくれることが得難いことと思います。
(自分は自分の状態と状況をなんとかしていくために学問からあぶれて勝手に考えてきた馬の骨なので、かりに同じことばを使ってもだいぶずれていたり、明後日の方向や問題のことを言っているかと思いますが、それでもどこか重なるところもあるかなとも思って発言させてもらっております。その点どうかご容赦いただけたら幸いです。)
さて、自分という場所の状態、または自分といういまの感受性を移り変えていくものとしての経験というとらえで映画を受け取りました。そして思ったことは、事実への向き合いと経験への向き合いは別々のものであり、ある問題に対しては、別々の二つのものに向き合う必要があるだろうということでした。
植民地主義の問題、戦争の問題、慰安婦の問題というような大きな括りの問題、あるいは金順岳さんが直面した問題という個人の問題にも、事実への向き合いと経験への向き合いが必要と思います。
事実と経験はあまり一般には分けられていないと思います。誰かの語りを聞いたり記録を共有することが「経験をシェアする」と言われたりしますが、語りを聞いたということや語りを記録をしたということはそれぞれ事実であって、それはまだ人の感受性を移り変えていく経験、ひいては記憶の継承というときに大きくかかわってくるだろうものとしての経験ではないと思えます。
事実と経験は、ある問題に向き合っていく際にどちらかを落としてすすめていくことはできないものと思いますが、時代的には「こと」としての事実の共有が問題への対処であり、記憶の継承といったときも、実態としては経験を抜きにした「こと」としての事実の詳細な共有、あるいはその大量の事実を規律訓練として個人に埋めこみ、あらかじめ正解として決められた機械的に固まった態度へと同化させることしかイメージされていなかったのでは、と思えます。
それに対して、映画「やさしく」は時代の思考に抜け落ちているもの、不可視化されているものとしての経験に光をあてているように思いました。
精神科医の神谷恵美子がハンセン病を患った人に対して、この方たちはわたしのかわりにこの状態をひきうけているのだという旨のことを何かに書いていたと記憶しています。映画でMeToo運動にかかわる人たちは、朗読という手立てによって、経験の展開を自動的に止め鎮圧してしまう自我の鎧に隙間をあけ、金順岳さんが自分たちのかわりにした経験を、自分たちの止まった時間を動かすもの、自分の新らしい生にとってかけがえのないものとして享受していたのではないかと思いました。
(経験ということばは、時代がことばにせずにすませているいろいろなものが十把一絡げにされておしこまれた納屋のようなことばで、このことも経験ということば以外をあてがうのが難しいのですが)金順岳さんにとって自分の消化能力をこえて背負わされた経験は、生のままに誰かにぶつけられるのではなく、妥当な距離と間接化(たとえば朗読・アニメ化)が施され希釈されれば、同質の経験をし、その消化のプロセスをすすめられずにいる人のプロセスをもう一度動かしていく力をもっているようです。神谷恵美子の「かわり」というのはそのことではないかと受けとっています。
経験という領域において、そこでじっさいに何がおこっているか、今まで何がおきたのかは、氷山の表出部分のように、意識で自覚できるものはわずかですが、記憶や経験とはどうもある個人が自分というフィルターで外界を受けとって解釈され整理されたデータのような、個人的な自己完結に閉じた矮小なものではなく、そのフィルターで受け取られ解釈されたものと同時に、自覚とは乖離された状態ではあるものの、過去から連なった歴史そのものが自分という場所に流れこんでいるのではないかと想像します。
以前の火曜会で、阪神大震災をリアルタイムで体験し報告するアナウンサーの語りを朗読する企画で、自分の知人二人が朗読の際に自分のうちに異質なものが流れこみ、朗読会が終わってもいつまでも残るその違和感や圧迫をなんとかしようとして震災を自分ごととして取り組みはじめたという事例を紹介しました。
経験というものが、単なる個々に解釈されるデータとしてしか認められず不可視化されているために、じつは自分というその場所に歴史そのものを流れこませている個々人の時間(そして歴史)の展開も止められているように思いました。しかし、危機に放りこまれ、追い詰められた身体性は、すでに自覚されたもの、社会環境からそのまま取りこんだもの程度で自己完結に構造化し固まった自分自身に亀裂をいれ、抜け出ていこうとする自律性も備えているようです。
そこにおいて、自覚において今までつながっていなかった歴史という水膜に、断片化し水たまりになっていた自身が水脈に接続され、自分が生みなおされる事態がおこるのではないかと思います。わたしは、今の固まったわたしの危機にさいして呼び起こされるものによって、矮小な個であるとともに歴史の連なりそのものとしてある自身の二重性を回復させていく契機を得ると思えます。またこのことがフラットで白紙の多勢に詳細な事実とあらかじめイメージされた態度だけを埋めこもうとしてうまくいかない、記憶の継承の問題のひらけとしてあるのではないかと思いました。
勝手に自己完結の結論に邁進しただけかもしれませんが、映画が自分の考えていることに続きをくれました。
大変ありがとうございました。
米田