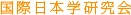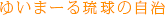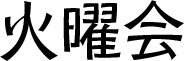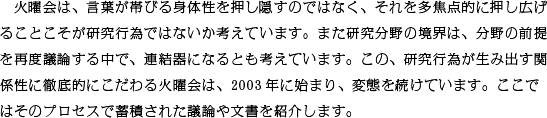火曜会通信(101)
やさしくきく––––映画『やさしく』上映会・トークイベントに参加して––––
元同志社大学大学院文学研究科生
松本菜々子
映画『やさしく』は、日本軍「慰安婦」として連行されたキム・スナクさんの一生を、とりわけ日本軍から解放された後の生活に重点をおいて辿る映画である。人の一生、しかも途轍もない苦しみと混乱の経験がその中に響いている一生について、時代も経験も全く異なる日本人女性の私は、何を受け取り、また何を語ることが許されるのだろう。この映画と向き合っている間、この問いが常に頭を占めていた。人の一生と何らかの仕方で関わるものが抱くべきこの問いは、私を「きく」態度へと導いていった。
「きく」、それも「やさしくきく」ことは、この映画のメインテーマの一つと言ってよい。ただし、「やさしくきく」態度がどのようなものかについて、何かしらの答えが本作で提示されるわけではない。むしろこの映画は、いかに「きく」べきかという問いへの切実な取り組みの痕跡(アニメーション、証言の朗読、スナクさんが海辺で笑う映像etc.)そのものである。決して答えの出ない問いに対するこの奮闘の跡こそが、本作なのである。
とはいえ、ここであえて「やさしくきく」とはどのような態度であるのかを考えたい。というのも、この問いは確かに簡単に答えが出ない(出してはいけない)けれども、この問いに関わり続けることはできるし、またそうすることは、この映画を通じてハルモニの一生と接した者の責任であると思うからだ。
「やさしく」と訳された本作の原題は、「보드랍게」(ポドゥラプケ)である。この「보드랍게」は手触りが「柔らかい」「滑らかだ」を意味する形容詞「보드랍다」(ポドゥラッタ)の副詞形である。それゆえ「보드랍게」を直訳すると「柔らかく」あるいは「滑らかに」となる。このように、「보드랍게」は第一に触覚に関する語であり、そこから転じて人に対する柔和な態度にも使用される(原語のニュアンスについては李啓三さんに多くをご教示いただいた。感謝申し上げる)。したがって「やさしくきく」とは、「柔らかく(滑らかに)きく」、すなわち「柔らかに触れるようにきく」ということになるだろう。
では、「柔らかに触れるようにきく」とはどのような態度だろうか。まず「柔らかに触れる」という動作は、触れる対象を傷つけないように力加減に細心の注意を払い、対象のありのまま形に沿って手を這わせるふるまいだろう。そして、触れる者がそのようにするのは、その対象が脆く、繊細であるからだ。つまり、触れる者はその対象の(脆さという)要求に従って、力加減を調節し、そのありのままを、手のひらを通じて受け取るのである。
このように「きく」ことが本作で提示される「やさしくきく」であるならば、ここでの「やさしさ」は(この言葉にしばしば含意される)同情的態度を示すのではないだろう。同情は、その感情を向ける対象と自分を切り離し、自分を対象との関係において優位に置く感情である。しかし、柔らかに触れるような「やさしさ」は、関係上の優劣を無効化する。というのも何かに触れるとき、触れる対象は同時に私に触れるものでもあるからだ。ここで結ばれる触れ合いの関係では、私と触れるものの間の権力関係は(たとえ一瞬だとしても)取り払われている。そこには対象との距離はなく、代わりに体温の交感がある。
本作で「きかれた」スナクさんの人生は、その形が定まらない早い段階に、日本軍による連行という形で踏み躙られた。スナクさんのその後の人生に、この苦難の経験がどれほど影響していたかを、外野の私が推し量るのには慎重でなければならない。ただ、この映画の中で何度も示されていたように、この受難は、スナクさんが自身の人生をありのまま語ることを困難にした。日本軍による連行の経験は「そんな話をするな」と暗闇に押し込められた。時代が下り政治の問題として「慰安婦」が取り上げられ始めると、遊郭や飲み屋での労働経験が知られると戦略上の不利になるとして、口を塞がれた。社会に蔓延る混血児への差別は、スナクさんに自身の息子を息子だとも言うことも憚らせ、「甥だ」と言わしめた。スナクさんの語りは、人びとによって、社会によって、政治によって、窒息させられていた。
こうした人生を「きく」=人生に「触れる」のがこの映画であり、その制作者であり、出演する支援者であり、私たちである。何度も言葉を奪われてきたスナクさんにとって、彼女の人生に「きく」ことで触れようとする手は、それまでの人生で何度もそうされてきたように、自身を押さえつけ、奪うものとして映っただろう。それゆえただ向き合うだけでは、スナクさんは今までと同じように沈黙してしまう。そうであるから、「やさしさ」が求められるのだ。それは、スナクさんが語るありのままを壊さないように、語りが示す傷跡を撫でるようにきく態度だ。そうすることによってはじめて、スナクさんの人生をきく=触れる側の体温で温めることができる。
このように「やさしくきく」ことによって体温の交感が起こるところに、それまで傷つけられてきたスナクさんの尊厳が立ち上がってくる。尊厳とは、自身を何かのための単なる道具としてのみ扱うことを拒絶する声のことだ。「やさしくきく」とはおそらく、この声に耳を傾け、その要求に従うことではないのか。
本作の「きく」試みが、スナクさんにとってそういったものであったかは、究極的にはスナクさんにしかわからない。ただ、スナクさんが砂浜で笑うとき、そして、スナクさんの証言に接した女性がある種の精神的開放を感じるとき、そこには「やさしくきく」ことによる体温の交感があったのではないだろうか。この映画の中には、人生と人生が触れあい温めあうこのような瞬間があったように思う。もしそうであるならば、この映画はスナクさんの尊厳が成立する場所、つまり「居場所」の記録と言えるのではないだろうか。