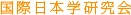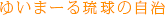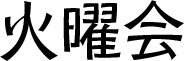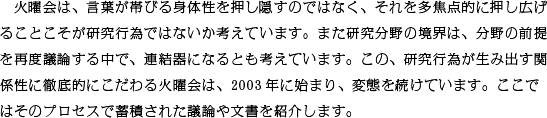火曜会(第43期)の予定
既に終了しています。
2025年春
同志社大学烏丸キャンパス志高館SK214
15時より
2025年4月16日 冨山
Ⅰ火曜会の経験
議論することの楽しさは、その議論が一つの正しい結論に収斂することでも、正しい主張に参加者が同意することでもない。楽しさとは、自分のこれまで考えてきたことが、ともに考えるという営みの一部となり、その営みに自らも参加していくことではないだろうか。その楽しさの強調点は、結論や主張にあるのではなく、参加ということにあるのではないだろうか。いま火曜会の経験といったとき、その経験とはこの参加の経験ということだと思う。つまりこの参加の経験は、「自分」ということと、「ともに」ということを架橋するところにある。
これはかなりやっかいなことだ。自分の経験を、感情をモーターにして自分たちにすぐさま拡大することは、よくある。とりわけ今はそうだ。そこでは「私」は、肥大化した「私たち」とすぐさま直結するような心地よい幻想もうまれる。そして今述べた参加の経験は、この「私」の拡張と一線を画するものでなければならないと、考えている。あえていえば経験という言葉は、この一線を画するところに据えられる必要がある。
バブルでふくれあがった欲望が消え始めた1995年、自分の欲望の拡張に忍び寄る不安が一気に自分たちに向かう動きを察知した藤田省三は、この「自分たち」を「安楽の全体主義」と呼んだ(『全体主義の時代経験』)。それは藤田の最後の書である。しのびよる不安を現状の安楽を肯定したい思いに浮遊する心性を、藤田はまずは「先験主義」とよび、またこうした心性が、もっともらしいリーダーや知識人を希求する基盤になるともいう。そして藤田にとってそれは、「経験の消滅」といいかえられている。こうした展開は、かつてはファシズムとも呼ばれたことであり、またポピュリズムともいわれるだろうが、重要なのは藤田がそれを介入すべき対象として見出していることだ。では経験とは何か。藤田にとって経験とは、自らの考えや欲望が変わる場であり、経験とはその場の中に参加することとして設定されている。藤田は「経験の中」という言い方で以下のように述べている。
経験の中では、物事との遭遇・衝突・葛藤によって恣意の世界は震撼させられ、其処に地震が起こり、希望的観測は混乱させられ、欲求は混沌の中に投げ込まれ、その混沌のもたらす苦しい試煉を経て、欲求や希望の再形成が行われる。
参加とは、経験の中に入ることといいかえてもよい。そして藤田のいう「再形成」においてはじめて「自分たち」にむかうプロセスが、おぼろげながら次第に浮かび上がるのだ。だがしかし、あえて注釈を加えるなら、藤田のいう安楽を初発から享受できない人々もいるはずだ。藤田の議論の立て付けとしてそうした人々を排除しているとは思わないが、参加の出発点には藤田の言い方だけではなかなか見えてこない生のありようがあると思う。
僕が耐えられるような場所に、この世界を、この自分をという存在を、つくり変えること。そのためには、世界が<現実>であり続けていてはダメだった。この鮮度を何とかしないと。自分という成立を自覚する瞬間が、<現実>の自覚とは別の形で実現してほしかった。だって、耐えられないのだから……。(上山和樹『「ひきこもり」だった僕から』2001年)
「場所」というものが、自分が成立する場所であり、上山はその場を自覚できる瞬間を鮮度という。この鮮度を確保することは、参加ということと重なる。これは文字通り藤田のいう「遭遇・衝突・葛藤」の瞬間でもあるだろう。そして上山はそこから始まるプロセスを、「動詞を解放する技法」といい(「動詞を解放する技法」『こころと文化』多文化間精神医学会学15巻1号、2016年)、またこの動詞の作動するプロセスを、自らを新たに「社会化する」ことともいいかえている。そこには自分と自分たちが一気に重なるのではなく、出会いと関係性が確保されている。この動的な関係性について考えるには、『ビッグイシュー』でなされた上山と精神科医の斎藤環との往復書簡とその破綻が重要なのだが、今は置いておく。
『土曜日』は人々が自分たちの中に何が失われているのかを想出す午後であり、まじめな夢が瞼に描かれ、本当の智慧がお互いに語合われ、明日のスケジュールが計画される夕である。はばかるところなき涙が涙ぐまれ、隔てなき微笑みが微笑まるる夜である。(『土曜日』創刊号1936年7月4日)
1936年に刊行された新聞『土曜日』の創刊号で、中井正一は「花は鉄路の盛土の上にも咲く」という文章を巻頭に書き、その末尾をこのように締めくくっている。中井は翌年に治安維持法違反で逮捕され、『土曜日』も終わる。
この中井のいう「鉄路」には、明らかに軍事的で侵略的な意味が込められている。また花という言葉については、「我々の生きて此処に今居ることをしっかりと手放さないこと、その批判を放棄しないこと」において咲く花とも述べている。そして中井はこの花を、「想出し」、「夢が瞼に描かれ」、「語合われ」、「計画される」場に求めたのだ。火曜会の経験とは経験への参加ということであり、「遭遇・衝突・葛藤」にもかかわらず場が確保され、そこから「欲求や希望の再形成」が始まることであり、それは花が咲く場だと、私は思っている。
Ⅱすすめかたについて
1火曜会の構造
火曜会の場は、三重の構造になっています。まずメーリングリストにおいて表現される場 ですが、これ火曜会で議論をした経験を持つ人々において構成されています。人数は 100 名 を超え、また東アジアや北米だけではなく、ヨーロッパ、北欧、北アフリカにまでひろがっています。こうしたメーリングリストの広がりの中で、定期的な火曜会が開かれています。またそうであるがゆえに、時々、「「言葉を置く」ためにやってくる旅人のような存在」(西川さんの「火曜会通 信」89 号 http://doshisha-aor.net/place/619/)として、登場する人々がいるのです。これが二つ目の領域。流動する旅人の領域です最後が直接対面で行われる火曜会です。こうした三重構造(旅人の文脈は構造というより流動系ですが)になっています。
また火曜会は「演習Ⅰ、Ⅱ」「現代アジア特殊研究」でもありますが、さらに対外的に使 える形式として次の三つがあります。一つは、火曜会を同志社大学<奄美―沖縄―琉球>研究センターによる「定例研究会」の通称としても使えるようにしています。今期でしたら定例研究会(第 43期)としたいと思います。研究センターの定例研究会、通称「火曜会」です。
もちろんこのような名称を用いるかどうかは、自由です。基本的には「火曜会」は「火曜会」なのであり、カリキュラム上の科目でもなく、「定例研究会」でもありません。ただ擬態を用意しておこうという訳です。
2すすめかた
事前に文章を読んできた後、一人ひとり順に注釈やコメントを話すようにしています。このやり方において見えてきたのは、言葉が堆積していく面白さです。それは契機と契機の連鎖といえるかもしれません。しかもその言葉たちが、 順に回すという力によってなされているので、しばしば「無理にでも」話そうとするという 性格を帯びるため、ある種の受動性が能動性に転化していくような出発点を一人一人の言葉が担っているような感触もあります。すべての参加者の「私」が出発点になっているので す。こんな言葉が、私たちの前の空間に次から次へと降り積もっていくのが、面白いのです。
それはあたかも一人ひとりが参加してノミをふるい、批評し合いながら一つの彫刻を作り上げていくような感覚です。火曜会ではディスカッション・ペーパーを前にした平等を前提に、一人ひとりが報告者であり、彫刻者です。
ただ問題もあります。次の展開、すなわち一人ひとりが一通りコメントし終わった後の全 体として議論を進めるのに時間がかかるという問題です。この時間にかかわって二点提起 します。ひとつは一人ずつのコメントについて以前から「パス」ということを気軽にいおうということが提起されています。この「パス」は、最初に述べたように、言葉が見つからないという重要な出発点でもあると思います。また最初の注釈やコメントを、最初の「読む時間」において各自できうる限り考えを準備しておくように心がけるというのもいいかもしれません。いま一つは、コメントの後の議論のすすめ方です。雪だるま式に積もっていくコメントを議論にもっていくのは大変です。またあせってすすめると多くの場合論点が見失われることがおきます。これをできるだけ防ぐのは一つには司会の役割ですが、司会だけではなく参加者が 目の前に堆積したコメント集合を丁寧に彫刻していくことが重要です。
3ディスカッション・ペーパーの配布について
議論をするための文章をディスカッション・ペーパーと読んでいます。このディスカッション・ペーパーを事前に配布します。前の週の土曜日までに MLで配布してください。またメモや箇条書きではなく短くても文章として作成してください。読むという行為をしっかりと確保しておきたいのです。
上に述べた火曜会の構造にもかかわりますが、配布をMLにかんして「誰が読んでいるのかわからない」「勝手に引用されたら」といった危惧があるかもしれません。ただ他方で、「議論の場に居合わせることがなくても、あるいは直接お会いすることはなくても、メーリングリストを通じて、既知の人、未知の人が、どこか別の時に、別の文脈で、このペーパーを読んでいるのかもしれない」(前述の西川さんの「火曜会通信」)というのは火曜会の広がりでもあり、またこのひろがりにおいて、先に述べた「「言葉を置く」ためにやってくる旅人のような存在」が確保されているともいえます。まずはペーパーの無断引用厳禁ということを再確認しておきたいと思います。
4司会についてなど
34期から司会を回り持ちにしています。今期も報告者が事前に司会者を指定することにしたいと思います。司会をどのようにやるか、たとえば積極的にコーディネイトするかど うかは、司会者におまかせします。そのうえで司会については、上記の2の最後で述べたように、コメントから議論へという展開をどうするのかということにおいて、少し意識的に考えてほしいと思います。またそのためには司会になった人は、全体のコメントに注意を向ける必要があります。
Ⅲ『火曜会通信』
火曜会にかかわる様々な文書は、http://doshisha-aor.net/place/644/に収められています。 火曜会が初めての人はぜひアクセスしてみてください。これまで火曜会で何をしてきたの かということがわかります。また『火曜会通信』というものがあり、それは火曜会での議論 をふまえた『通信』です。しばしば『通信』を楽しみにしているという声が届きます。それ は上記の火曜会の構造の第一の層にもかかわるでしょう。ですが、この間通信は出せていません。ぜひ執筆してください。文章は私のところへ送っていただければ掲載します。
Ⅳ雑誌『多焦点拡張 MFE』について
創刊準備号を入れ5号まででました。5号の特集は「留置と拘束」です。近日中に6号がでます。
『多焦点拡張 MFE』については、以下を見てください。
https://sites.google.com/view/webmfe/
http://doshisha-aor.net/mfe/808/
この「MFE」は「多焦点的拡張主義(Multifokaler Expansionismus=MFE)」の略語です。この言葉は、1960 年代後半に西ドイツのハイデルベル ク大学医学部精神科の助手や患者を中心に生まれた社会主義患者同盟(Sozialistisches Patientenkollektiv=SPK)が遺した言葉で、それは、「精神病」が体現する禁止の領域を人々が集まる場所(暖炉)に変えていく運動を意味しています。また「焦点(fokus)」という言葉には、禁止と暖炉の二つの意味が重ねられています。さらにまたここでいう拡張、すなわち広がるということとは、同質な多数派を構成していくことではなく、自らの住まう既存の世界がその存立前提として禁止してきた領域を問い、禁止された領域とともに変わっていく運動としてあります。また焦点とは、このような既存の世界の前提を問う動態の中で見出される場なのです。
SPK については詳しくは冨山の『始まりの知』を読んでいただきたいのですが、ともあれ学の領域や区分にかかわる言葉ではなく、禁止を暖炉に作り変え続けていく運動 (expansionismus)を、雑誌名に掲げました。それは、雑誌『MFE』が担う、思考の場の新たな生成と連結が、既存の世界の前提を問い続ける運動になると、確信しているからに他なりません。こうした雑誌と運動について、「雑誌の「雑性」について」という題で『思想』2023 年 3 月号の「思想の言葉」で書きました。MFE についても言及しています。よければ読んでください。https://tanemaki.iwanami.co.jp/posts/7022
Ⅴ金曜の授業
金曜3限 「危機の中の表現」 SK214
参加を希望される方は、ご連絡ください。今週からです。以下シラバスをペーストします。
戦争,災害,パンデミックとして語られる状況を非常事態と呼ぶならば,非常事態を言葉で表現するとはいかなる営みなのだろうか。その際前提としておきたいのは,非常事態が既存秩序の崩壊だとするなら,その「既存秩序」には言語的秩序もふくまれるということだ。そして学知もこの秩序の一部に他ならない。したがって出発点になるのは,冷静な分析ということではなく,言語的秩序が崩壊する中で突出してくる言葉にできない感覚や,説明できない視覚であったりするだろう。またこうした出発点を経験の領域とするなら,まずは言葉にならない非常事態の経験をいかに言語化していくのかということが,課題となる。またその言語化のプロセスは,他者との関係性の中で遂行されることにも注意したい。またさらに,秩序の崩壊を非常事態だとするなら,その言語化は既存秩序とは異なる未来を先取りしようとする営みでもある。しばしば崩壊には回復や復帰が対案として提出されるが,こうした思考においては、非常事態はあってはならない間違いとしてある。しかしそこから別の未来を引き出そうとする営みにおいては,それは新たな未来への始まりとしてあるのであり,こうした始まりはしばしば回復や復帰の阻害物として認定されることに留意したい。講義では,日本の近現代にかかわる出来事を具体的に取り上げながら議論を進めるが,同時に非常事態は,今の問題であることを絶えず確認しながらすすめていきたい。
Ⅵその他
(1)4月22日(火曜)に、大阪心斎橋にあるルイ・ヴィトンの展覧会スペースに行きます。貸し切り状態です。キュレイターの渡辺文菜さん(李真煕さんの友人)からのメールでは、以下のようにありました。当日は渡辺さんが案内をしてくれます。10時半にビルの前に集合。渡辺さんは、たぶん火曜会にもいらっしゃいます。以下渡辺さんからのメールです。
現在エスパスルイ・ヴィトン大阪では、5月11日まで、ドイツ人アーティスト、ウラ・フォン・ブランデブルクによる「Chorsingspiel」展を開催しております。またもや映像インスタレーションなのですが、前回とはまた異なる雰囲気で没入感を感じていただけるかと思います。舞台美術を背景にした、「垂れ幕」を効果的に使用した作品で、なおかつ映像も詩的で、浮遊したような世界観で、異世界に迷い込んだかのような気分が味わえます。
(2)『やさしく』上映会
廣野さんを中心に準備しています。このドキュメンタリーは今年一月に立命館大学でも上映されました。その時のチラシです(https://www.ritsumei.ac.jp/file.jsp?id=642180)
このチラシの説明にもあるように、植民地主義とその後の冷戦が重なり合う状況とその中で生きてきたということが、いま日本軍「慰安婦」問題と呼ばれる領域において問われているのでしょう。
上映会は5月31日(土曜日)を予定しています。またそのための学習会を連休明けの5月9日(金曜)の15時から行います。場所は冨山の研究室か、どこかの演習室でおこないます(近づいてきたら連絡します)。ぜひ集まってください。また上映会の準備などにぜひ参加・協力をお願いします。
(3)火曜会メンバーである佐々木薫さんよりの手紙です。ぜひお読みください。
京都を離れてからもう9年経つのかと驚いています。名古屋へ戻って就職してから紆余曲折を経て、いまはVC(ベンチャーキャピタル、スタートアップ企業へ投資するファンド)で投資家サポートの仕事をしています。
現在所属している会社で、人文研究を支援するための給付型奨学金プログラムを開始しました。元々、所謂「理系」分野の基礎科学研究向けの給付型奨学金を7年近く行っており、今年から人文領域の研究者を支援したい、という想いから開始しました(立上げ・運営に自分も少し携わっています)。
応募方法は下記のフォームから記述し回答いただく形式です。学振応募などの時期と重なりますが、少し〆切は遅めなので、少しでもご興味ある方へ届いたらと思い、可能であれば火曜会メンバーの皆さんなどへ広めていただけますでしょうか。
***
ネオリベラリズムの震源地、capitalの集積地に居つつ、近い問題意識を持つ人も居ることを発見し、capitalサイドからどうにか連帯できないか、という取り組みです。無批判に「知」を称揚するわけでも、傲慢な「支援」という形ではなく、対話ができないか?という試みです。
なぜ対話なのか。いわゆる「在野」に長くいますが、インターセクショナリティといった交差性・複層性への(一層の)重視を肌身に感じています。複雑化していく社会の流れのなかで、個別ではなく包括的に課題を紐解いていく視点は、事業を通じて社会に携わっている者にも必要になると考えています。やや異なるかもしれませんが、研究領域でも学際性や領域横断的なアプローチはずっと取り組まれ奨励されてきているなか、「領域の横断性」は(学問領域間もですが)産業領域間・業界間(Biz とAcademia、Biz と Socialsectorなど)との交流、接合がもっと生まれると良いなという想いを、本奨学金の構想段階から強く持っています。立場やアプローチは異なれど、「まだ見ぬ未来を構想・想像する営み」を同じく行っているのではとも思い、先ずは支援という形でですが、連帯していけたらと思っています。(弊社にとっては、「実学」とされる経済・経営学以外の人文・社会学領域の研究に近づく非常に重要な取組とも考えています。)
***
自分は経済的な要素も含めた体調不良で研究の道を断念してしまったので、そんな懸念を持つ人がいるならば、少しでも不安が和らいだ状態で研究へ存分に専念してもらえたら、またいわゆる人文領域(の研究)の重要さ・注目を高められたらという想いも個人的に込めています。
<奨学金の内容及び趣旨>
✅1人あたり50万円給付(最大10名)(用途不問、PC購入可)
✅人文系分野の研究に取り組む研究者 ※対象者要件はサイトをご確認ください
→領域に制限無し。応募時に「社会・未来への接合」を記載いただけたらOKです。
✅締切:2025年6月30日 23:59
✅応募方法:https://forms.gle/eE9prH3Vo8h8bTvcA
■人文奨学金HP:https://anrivc.notion.site/ANRI-1d509d749d7980ab8902da1091883e4a
■プロジェクト担当者 中路(なかじ)さんのノート
https://note.com/nakaji_memo/n/n470a05ca4ec1
■プレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000040191.html
Ⅶ今期日程(題は仮のものです。日程がまわってきた改めて連絡があります。)
4/23 映画『アドレセンス』を見る
案内 李啓三
5/7 中島梓と「少女」
報告 手嶋彩世子
5/14 魂という居場所
―石牟礼道子の場合―
報告 李啓三
5/21 マリアローザ・ダラ・コスタ著『マルクス「労働日」の解説 ー『資本論』講師の備忘録―』を中心にダラ・コスタとマルクスの関係を探る
報告 姜喜代
5/28 「50年問題」から1970年代初期にかけての京都市日本共産党の再建の過程を把握する試み
報告 ウラジミール・マリク
6/4 ダナ・ハラウェイを読む
案内 内藤あゆき
6/11 経験を取り戻すには
報告 米田量
6/18 『チェポ 栄子』韓国KBS (2024)を見る
案内 李真煕
6/25 地域社会と多文化共生
報告 玉尾章代
7/2 『あさつゆ』を読むⅡ
報告 山口沙妃
7/9 暴力の「あと」を聞き、書くこと
報告 廣野量子
7/16 学校という場
報告 大藪瑞穂
7/23 自主夜間中学における多文化共生
報告 玉尾文代
この後、持ち寄りパーティーをしましょう