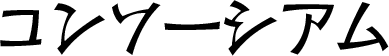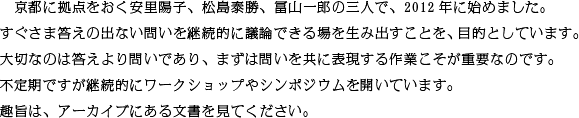冨山一郎「独立を発明する」
(『沖縄タイムス』2014年10月23日、24日掲載)
独立を考えることは、すぐさま国家の設計図を描き、その善し悪しを論じることではない。少なくともそれだけではない。今の沖縄を取り巻く状況を念頭に置きながら、紙面の許す限り、独立という言葉がもつ問題の広がりを考えてみたい。
まずそれは、新しい政治である。ロバート・D・エルドリッヂは『沖縄問題の起源』(名古屋大学出版会、2003年)において沖縄に基地が集中している現状を批判しながらも、それは「地域の事情」であり、いわゆる「基地問題」は日米間で解決しなければならない政治課題だとした。そこでは沖縄は、「事情」であって政治的な主体にはなりえず、政治は主権をもつ日米において構成されている。またこうした枠組みは、基地に対する判断を越えて、広くいきわたっているといえる。だが独立とは、既存の政治においては「事情」とみなされている領域が、新たに政治化するプロセスであり、あえていえば政治内容ではなく、政治領域それ自体が問われるプロセスなのだ。
このプロセスには、二つのモーメントがある。一つは既存の政治から降りること、あるいは離脱するというモーメントであり、もう一つは、政治を新たに構成する、すなわち作成にかかわるモーメントだ。いいかえれば独立とは、既にある主権や国家の概念をあてはめることではなく、新しく創造される政治なのであり、それが新しいものであり続けるには、既存の政治からの離脱という契機が、常に確保されていなければならないのだ。
ここで、離脱自体が政治だといういい方も、できるかもしれない。あるいは、運動現場で生成する多様な関係性こそ新しい政治だという人もいるだろう。だが独立の要点は、離脱を既存の政治との関係の中でいかに代表するのかというところにある。この代表性こそ、二つ目のモーメントにかかわるのであり、またこの点にこそ、独立が抱え込む困難さがあるのだ。すなわち代表性は一方では既存の政治領域へのアクセスを準備する。それは準備されたテーブルにのることであり、秩序の反復でもあるだろう。他方で代表することにより抱え込まれるむ存在は、既存の政治から離脱し続ける。作成にかかわるモーメントとは、離脱者を、まさしく離脱する状況において代表することのであり、そこにでは既存の政治において代表することと、その政治への根源的な否定性を確保することが一体としてある。
この一体化にこそ、独立という問いがある。いいかえれば、離脱と作成の二つのモーメントが構成する困難さを抱え込むことによって遂行されるプロセスにこそ、独立という問いが存在するのだ。また新たな政治は、頭の中で描かれた既存政治の外部に待機している訳でもなければ、現場という言葉におきかえてすむことでもない。それは、この困難さを抱えむ者たちにおいて、新たに発見され発明され続けるのだ。かつて新川明が「土着と流亡―沖縄流民考」(『現代の眼』1973年3月)において、主権への「復帰」が完遂されたまさしくその瞬間に、住民ではなく「土着にして流民、流民にして土着」という沖縄人のありようを新たな政治的主体として見いだそうとしたこととも、それは関係するだろう。そこには、流亡者をいかに代表するのかという問いがある。あるいは主権への帰属が政治の大前提を構成した「復帰運動」の内部から、主権からの離脱の契機を引きずり出し確保しようとした清田政信の「帰還と脱出」(沖大文学研究会『発想』3号、69年)における思想的営為も、この困難な一体化にかかわる。念のために付言すれば、こうした困難さを引き受ける営為は、復帰に対して反復帰を論壇的に対峙(たいじ)さすことではない。
次に離脱ということを確保するために、今日に至るまで「基地の島」を維持し続ける統治とはなにかということを、問わなければならない。たとえば主権において構成される既存の政治領域が重視されるのは、「基地の島」が日米の主権的法制度において維持されていると考えるからだろう。だが私には、そうは思えない。なぜなら沖縄は一貫して、主権的法制度の例外におかれ続けているからだ。戦後という時間に限定して考えても、占領と潜在主権、密約、さまざまな特措法、そして今、刑事特別法なる例外措置が登場している。こうした法の停止状態とでもいうべき例外状況から浮かび上がる統治こそ、「基地の島」にかかわる政治の問題なのだ。そして今重要なのは、法制度を越えた無法な暴力が直接社会に介入してくる統治それ自体の問題を、正面から見据えることではないだろうか。たんに例外を普通にかえること、すなわちより完全な主権への帰属を未来への道筋として想定するのではなく、かかる統治それ自体からの離脱を起点として根底的に据えるところに、独立という新しい政治が求められる根拠があるのではないか。また既存の主権に依拠しないという点で、主権を横断する抵抗運動と独立は、問いを共有している。
政治学者二コス・プーランツァスは、こうした無法な統治を、例外ではなく常態としての国家の非合法性とよんでいる。この非合法性は、時には主権に還元されない国家の相貌として、また時には国家を越える超主権的な統治として顕在化する。冷戦の中で展開した越境的なミリタリズムは、主権をアクターにした国際関係というよりも、主権的存在と主権を越えた統治の野合の中で、この非合法性の領域が世界にまん延していく事態だったのではないか。そこでは軍事的暴力は、たんに同盟関係や国籍において意味づけられる武力ではなく、主権的法制度の停止状態において特徴づけられるのではないか。それはまた、自国の軍にかかわる戒厳状態と他国の軍による占領状態が地続きで展開する統治の拡大でもある。路上に装甲車が当たり前のように常駐し、洋上に艦艇が待機している風景の中で遂行される問答無用の拘束や追放は、今日さらに拡大している。無法な統治において求められる独立とは、かかる風景にかかわって新たに発明される政治なのだ。
今こうした無法な統治が、様々な例外的形態をまといながら、どのように世界に登場しているのかについて詳しく論じる余裕はない。だが、冷戦において登場した沖縄という「基地の島」が、今もなお法の停止状態とでもいうべき統治の中にあることは間違いない。この例外状況は、たんに日米間の従属的関係に起因するのではなく、国家の非合法性の問題なのだ。このことに関連して、最後に一つだけ述べる。それは、国民という主権的一体性の欺瞞(ぎまん)という問題だ。戦後日本の主権的一体性は、この非合法性を「地域の事情」として沖縄に限定し、地理的に区分し例外化することで成立している。それはいわば、主権に還元できない国家の非合法性をあらかじめ排除して成り立つ否認の共同体でもあるだろう。かかる国民的一体性こそ、主権国家日本の戦後という歩みに他ならない。独立とは、かかるあらかじめの排除を根底から問い直す政治でもあるのだ。また「基地の島」からヤマトへの「県外移設」という主張は、この共同体の自画像の根幹にかかわるがゆえに、日本社会において無視され、場合によっては排撃され、またしばしば別の政治課題におきかえられるのだろう。
「県外移設」は、たんなる基地のフォーメーションや用地探しのプランではない。問われているのは、左翼政治も含めた日本の戦後という土台それ自体であり、その土台を構成する領土的な時空間である。かかる問いから始まる事態は、戦後を前提にした日本政治内の対立構図におきかえられるものでもなければ日米同盟一般に還元される問題でもなく、日本という共同体の中で否認され続けてきた存在が、顔を持って登場するプロセスに他ならない。日本の戦後という時空間を食い破りながら登場するこの者たちは、あらかじめの排除を書き直し、「地域の事情」という嵌(は)め殺し的ふちどりを無効にしながら、国家の非合法性からの離脱を確保し続けるのだ。かかる点で「県外移設」は、独立とともに考えなければならない問いでもある。