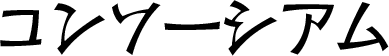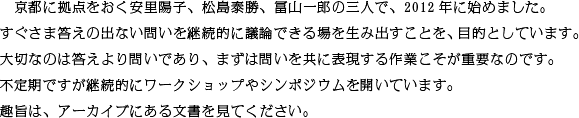冨山一郎『流着の思想』(インパクト出版会)ハングル版(Geulhangari Publishers)の序
表題「確保する」
2011年3月11日の直後、東京電力福島原子力発電所の原子炉が冷却できないというニュースが流れた時のことは、決して忘れることができない。それはまるで、些細なトラブルであるかのような報道だった。政府もマスコミも、そして専門家も、声をそろえて安全を合唱したが、すぐさま「メルトダウン」という言葉が頭に浮かんだ。そしてこの言葉から始まる事態は、安全の大合唱が空虚な響きとなっていく中で、次第にはっきりとした輪郭をもって人々の生を蔽いはじめたのだ。今も進行中である。
「メルトダウン」。それは決して新しい言葉ではない。反原発闘争を多少なりとも知っている人ならば、この言葉が意味する壊滅的事態を既に知っていたはずだ。だから冷却できないというニュースを聞いた時、なぜ知っていたのにここまで来てしまったのかという激しい後悔と、今からでも遅くはないという決意が入り混じった感情が、湧きあがったのを覚えている。
原子力を問うことは、戦後という時間総体を問うことだ。乱暴にいえばこの国は、帝国の崩壊を受け止めることのないまま「戦後」という時間を刻み出したのであり、あえていえば戦後を歩むことに失敗したのだ。だからこそ3月11日は、この国の戦後総体を、もう一度問い直す契機でもあった。いまからでも遅くはない、やり直せる。そして、その希望は捨ててはいない。だがしかし、現在進行中の事態は、三度目の破局に向かっているようだ。
現前に広がっているのは復興という名の隠ぺいであり、不都合な存在を問答無用で遺棄していく国家の暴力性である。そしてその国家の暴力性は、いま沖縄に集中的に顕在化している。沖縄に問答無用の暴力が集中することは、今に始まったことではない。本書ではその歴史を、系譜学的に辿ろうとした。乱暴いえばこの暴力が維持してきた歴史は、この国が何を放置し、隠し続けてきたのかということにかかわる。問題なのは、日本という国家である。
また国家の暴力性は、今日具体的に登場している「憲法改正」という政治過程に、端的に見いだすことができるかもしれない。しかし私が最も嫌悪するのは、「ニッポン」という空虚なかけ声とそれを発する者たちの醜い顔であり、「ニッポン」にしがみつく心性が蔓延する中で生じていく言葉の無残さだ。そしてこの無残な言葉は、既に知っているはずの壊滅的状況を忘れようとする無駄な努力にも見える。言葉は、現前で起きている状況を回避することに専念し始めたのだ。「メルトダウン」は、直接言及されないことにより言葉を土台から侵食している。
私の親戚に、子どもと共に関東地区から避難している人がいる。自ら放射能の線量計を持つ彼女とその息子の、生き延びようとする固い決意の横で広がる空虚な「ニッポン」コールと無残な言葉。私が安倍を最も嫌悪するのは、その政権が担う政治というだけではなく、この者が、彼女を追い詰め孤立させる醜い顔と無残な言葉そのものだからだ。
そしてこの「ニッポン」に包まれた言葉が蔓延する中で、沖縄の声は遺棄されていく。だからこそ問答無用の暴力は、言葉の問題として論じなければならない。またそれは、この「ニッポン」からの離脱においてこそ浮き上がる世界を確保する言葉たちを、探すことでもある。生き延びなければならない。
長年の友人が京都に来た時、ウィスキーを飲みながら本書の感想を話してくれた。彼が話したのは、「帯電する」そして「確保する」という二つの動詞だ。本書で多用されるこの二つの動詞の響きに、強く魅かれたという。気付かなかったことだが、そこには言葉の手触りを欲している自分がいるのだろう。また同時に、いま公とされる空間を行きかう言葉への嫌悪とでもいうべき身体感覚が、そこにはあるのかもしれない。言葉の無残さは、良心的知識人も含め、この国の論壇やアカデミアに広がっている。壊滅的状況に対する言葉の準備が、できていないのだ。
外の力に巻き込まれること、そしてそれを引き受けること。流着とはこうした一連の動きのことを指す。そしてこのような受動性と能動性が重なり合うところに、言葉の領域があるように思う。私は、巻き込まれ、引き受けるというこの動きを、帯電したいのだ。そしてこの言葉の領域を、帯電した身体と共に確保したいのだ。それは思想の身体性とでもいうべきものかもしれない。また「流着の思想」とは、巻き込まれ、引き受けるという動きを身体化し、問いを立てつづける言葉の在処を確保することなのかもしれない。この在処は、フランツ・ファノンの『黒い皮膚・白い仮面』の最後の末尾にある、「おお、私の身体よ、いつまでも私を、問い続ける人間たらしめよ」という叫びのような宣言が掴もうとする、未来でもあるだろう。
長年の友人である藤井たけし氏により気づかされたことだが、私の文章では動詞を概念化することが多く、しかもその動詞が、主語と述語を生成させるモーターになっている。その時動詞は、受動態とも能動態とも区別のつかない意味を帯びていくのであり、あえていえばそこには、言葉の存在論的な身体性があるのかもしれない。
いうまでもなく、翻訳とは、翻訳できないある種の身体性を発見し、それを言葉に(再)刻印してくことでもある。そしてその身体性は、しばしば言葉を記した本人には感知できず、翻訳者こそが記せる領域だ。そしていま、ハングル版の『流着の思想』ができあがったのは、鋭敏な言語感覚と言葉にかかわる深い知識を持つ沈正明さんだからこそだと思う。かかる意味で本書は、私と彼女の共同作品である。正明さん、本当にありがとうございました。
1月29日未明
冨山一郎