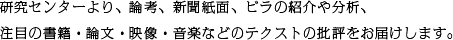国場幸太郎における民族主義と「島」
国場幸太郎における民族主義と「島」
冨山一郎
報告原稿:シンポジウム「『島ぐるみ闘争』はどう準備されたか」2013年12月23日 タイムスホール
京都から来ました冨山です。今日ここでお話ししたいと思っていることは、国場さんが1962年に書かれた、二つの論文についてです。この二つの論文については、この本でも複数の方々が言及されていますが、題名を改めて述べれば、「沖縄とアメリカ帝国主義―経済政策を中心に」(『経済評論』1962年1月号)と、「沖縄の日本復帰運動と革新政党―民族意識形成の問題によせて」(『思想』452号、1962年)です。今順に経済評論に掲載された方を一つ目、思想に掲載された方を二つ目としておきます。
私は国場さんの晩年に森さんに誘われて議論をしたことはありますが、直接的関係があったわけではなく、私にとって国場さんは、まずこの二つの論文において出会ったといえます。もう12,3年近く前になるでしょうか、朝の十時に沖縄にかかわる論文を読む会というのを私の自宅で森さんと他数名でやっていました。「十時の会」といっていたのですが、そこでこの二つの論文を森さんが持ち出してきて、一緒に読んだように思います。その時は、論文における国場さんの思考の緻密さ、そして明晰さに心を撃たれた記憶があります。またこの論文が1962年にかかれたということの意味についても、驚きとともに議論をしたように思います。
したがいまして、私の場合今日は、どこまでも文章を通じて見出される国場さんの姿を述べることになります。その姿は、国場さんを直接ご存知の方々からすれば、場合によっては、ずれているかもしれません。ですが残された文章においてこそ議論できることがあるとも思います。そしてまあ、きっとあるに違いないということで、今日登壇させていただきました。そしてこの間、この二つ論文を改めて読み直していたのですが、まさしく今の状況において再読されるべきものであると確信しました。もちろんこの二つの文章は時代状況的なものですが、今日は、この二つの論文を読み、その今日的な意味を考えるということで、発言させていただきます。
その際、議論の焦点にすえてみたいのは、意外に思われるかもしれませんが、民族あるいは民族主義という問題です。この多くの手あかがついた言葉に対しては、すぐさまそれを嫌悪し、否定的に解説したり、また逆にそれを動かし難い運命として全肯定する態度が存在するでしょう。ですが、こうした二つの立場を意識しながらも、今日は国場さんの思考に即して、注意深く考えていきたいと思います。
まず国場さんは二つ目の論文「沖縄の日本復帰運動と革新政党―民族意識形成の問題によせて」において戦後沖縄を、三つの時期に区分しています。第一期を1950年まで、すなわち沖縄群島知事選挙までとし、第二期を島ぐるみ闘争をはさんで通貨がドルに切り替えられる1958年まで、そしてそれ以降を第三期としているのですが、これらの時期区分の底流には一貫して民族意識、民族運動、民族主義などを、どのように構成していくのかということが問題意識として存在しています。
たとえば第一期から島ぐるみ闘争に向かう第二期の移行において国場さんは論文の中でで、「住民の民族意識を再構成する必要」がでてきたと述べ、また第二期から第三期においてもこれまでの「民族主義」ではだめで、あらたにそれを再構成していかなればならないと述べています。民族を構成する。たびたび登場するこの表現に、まずは注目したいと思います。民族は運命的な前提ではなく、構成するものだというわけです。また後でも議論しますが、この第二期から第三期における民族主義の再構成という問いは、同時に瀬長亀次郎氏を軸とした沖縄人民党のあり方への批判として存在します。そこではこの第三期の沖縄における民族主義が、国場さんにおいては否定的な展開を遂げていったという認識が前提になっています。そのような意味で、この論文はまさしく現状介入的な政治論文であり、その介入の焦点の一として「民族を構成する」という表現が登場しているといえるでしょう。
また民族や民族主義ということばにおいて捉えられている問題は、第一期における仲宗根源和氏らの独立論であり、復帰運動における日本への民族的一体感ですが、やや議論を先取りしていえば、そこには沖縄か日本かという民族区分的な問題というよりも、民族という領域それ自体への極めて深く又冷静な思考が存在しています。またさらにいえば、ここでいう民族とは、島ぐるみ闘争における「島」という問題であり、今に引きつけていえば「オール沖縄」ということにもかかわります。
ところで国場さんの二つの論文にそくしながら、こうした民族という領域にかかわる議論を立てるために、最初に少しだけ私の方からの論点を提示しておきたいと思います。私が議論の補助線としてここでもってきたいのは、アルジェリアの民族解放闘争を指導したフランツ・ファノンの民族文化にかかわる議論です。ファノンは次のように述べています。
民族文化とは、民衆が自己を形成した行動、自己を維持した行動を、描き、正当化し、歌いあげるために、民衆によって思考の領域においてなされる努力の総体である(ファノン『地に呪われたる者』)。
ここでいう努力の総体とはフランス語ではL’ensemble des efforts、ややくどく訳しなおせば、「複数の努力の調和あるいは合力」ということです。そこでのポイントは、民族が行動という力にかかわる概念であるということであり、また複数の異なる動きが重なり合っていくプロセスにかかわることだという点です。またこの文章だけだと分かりにくいかもしれませんが、注意すべきはファノンにおいてこの調和あるいは合力は、バラバラになっているモノのたんなる足し算や最大公約数ではないという点です。それは既存の秩序においては区分された集団が、その区分を成り立たせている前提である秩序自体を問う中で、集団が変容し、これまでになかった関係性と集団性が見出されていくというプロセスです。すなわちいいかえればそれは、それぞれが変わりながら繋がっていくというプロセスであり、一体性や強引に一つにまとめるということではありません。異なる者たちが、自らを変えながら合力を作り上げていくプロセス、やや理念的にいえば、諸集団の前提を動かさないまま表面的に足し算をしていくことではなく、前提それ自体が別物に変わっていくプロセスです。
このファノンの議論を念頭に少し先取りしていえば、国場さんが民族や民族主義といった言葉で示そうとしているのは、民族という言葉においてすぐさま思い浮かべる均質な同一性や人類学的カテゴリーなどではなく、総体としての力を確保し続けようとするプロセスです。そしてこのプロセスがプロセスとして成り立つためには、前提を問い続ける作業が必要になります。では国場さんにとってこの作業は、だれが担うものとして想定されているのでしょうか。この問いを抱えながら次に、国場さんの示した時期区分に即して少し考えてみます。
先ほども述べたように、第一期において議論されているのは、仲宗根源和氏らの沖縄民主同盟ですが、そこには同時に日本共産党の戦後初期の沖縄人連盟に対して出された「沖縄民族の独立を祝う」というメッセージにみられる独立論もとりあげられています。そして国場さんはこうした独立論を、反軍国主義、反天皇制という点において評価しつつも、郷党的、すなわち村的で閉鎖的な共同体に根ざしており、またアメリカ解放軍規定という誤った認識の産物であるとして批判します。
私自身は、この時期の独立論的な主張については、それが沖縄の外に流出した人々のネットワークと共にあり、またその際、あの沖縄人連盟とともにハワイやカリフォルニア、あるいは南米といった地域に越境的に広がった沖縄出身者のネットワークが大きな意味を持つと考えているので、閉鎖的な村的共同体という国場さんの評価に対しては批判があります。また、アメリカや米軍のヘゲモニーの問題も日本共産党の解放軍規定ということではなく、こうした越境的なネットワークの広がりと米国および米軍の関係の問題として、注意深く議論しないといけないと考えていますが、いまはそれは、すこしおいておくことにします。
さてこうした国場さんの独立論批判において注目すべきは、国場さんより二年早く東京大学の経済学部を卒業した日本共産党の上田耕一郎に国場さんが言及しながら、日米による沖縄支配について検討している点です。そこで国場さんは、民族という領域について、日本資本主義においては実はそれは重要ではなく、他方でアメリカ帝国主義のヘゲモニーにおいては意外に重要であると述べています。つまりどういうことかというと、日本資本主義は民族的差別や民族的階層構造にそれほど資本蓄積の基盤においている訳ではなく、したがって単に支配されていた沖縄民族の独立ということだけでは日本帝国主義の歴史に対峙することはできないのであり、またアメリカ帝国主義の支配においては民族が支配の回路になっており、米国が支配のために設定した、あえていえば上からの民族主義を乗り越える民族主義が必要とされている、というのです。そしてこの二つの点において郷党的、村的な独立論は不十分であり、民族主義は再構成されなければならないとしたわけです。この再構成といういいかたは、先ほども述べたように国場さんの言葉ですが、同じく国場さんの言葉を借りれば、反軍国主義的性格を持つ村的な独立論を弁証法的に止揚しなければならないともいってます。いずれにしてもそこにあるのは、米国が提示する民族主義を乗り越える挑戦的な民族主義であり、かつ資本主義とも対峙できる民族主義ということです。そしてこの論点こそが、民族主義再構成のポイントになるのです。
くりかえしますが、この再構成で問われているのは、沖縄の解放運動において民族という領域をどのように設定するのかということであり、沖縄か日本かという帰属の問題ではありません。また民族とは政治の前提ではなく、まさしく不断に見いだされ、再構成され続ける対象であるといってもいいかもしれません。ただこうしたことをふまえた上で、国場さんにおいて民族が沖縄の民族であるということは、動かし難い前提として存在します。そこでは国場さんは、「沖縄のおかれた歴史的社会的条件」といういいかたをして、民族という言葉を使っています。すなわちこの「沖縄のおかれた歴史的社会的条件」において、沖縄の政党には日本の政党とは異なる「民族的性格」があると述べ、いわゆる日本の政党との系列化を批判しているのです。またそれは、後にこの本にある国場さんの文章の中で「沖縄の党」といういいかたで述べられていることにもつながっていると思います。
ともあれこうした再構成において、第二期の島ぐるみ闘争が問題になります。すなわち独立論から新たに再構成された民族主義こそ、島ぐるみ闘争に他ならないという訳です。そしてその再構成のプロセスにおいて国場さんが注目するのが、1950年の沖縄群島知事選挙です。この知事選挙が米軍支配の回路としての自治であることはいうまでもありませんが、国場さんはその上からの自治を自分たちの自治として獲得していくプロセスをそこに見出し、それこそが典型的な民族運動なのだと述べています。それは日本への帰属を求める日本復帰運動の始まりではあるのですが、国場さんにとっては日本ということが焦点ではなく、民族主義の再構成が重要なのであり、その再構成の軸なっているが自治という問題でした。民族とは自治の問題であり、いわば先ほど述べた米国の支配の回路としての民族を自らの民族として乗り越えていくプロセスが、この群島知事選挙だったというわけです。さらにこの民族の再構成において国場さんは、沖縄人民党が郷党的、村的集まりから民族戦線構築に変化したとも述べています。
ではこの変化は一体何だったのでしょうか。1962年の論文では全く触れられていませんが、そこには明らかに国場さんがいう「沖縄の党」すなわち非合法共産党の存在が念頭に置かれていたことでしょう。この点において、あえてこの「沖縄の党」ということを問題にすれば、それは単に人民党の地下組織ということだけではないと私は考えます。それはまさしく先ほど少しふれたような、複数の努力を組み合わせていくプロセスとしての党だということです。つまり何らかの固定的な利害を代表するのではなく、利害を構成している前提自体を問い、新たな関係を見出していく努力の総体としての党なのであり、それはいわゆる政党に還元されるものではありません。そしてそこに国場さんは民族主義の再構成を重ねた訳です。いいかえればこの本や資料集で示された非合法共産党の存在と1952年の労働者のストライキを島ぐるみ闘争の底流にすえるということは、郷党的で村的な集団が沖縄解放のための民族主義に変わっていくプロセスとして、島ぐるみ闘争があるということに他なりません。国場さんが島ぐるみ闘争を自然発生的なものではないといいつづけるのも、この政党とは異なる「沖縄の党」の存在を念頭においていたからであり、民族主義の再構成、すなわち努力の総体としての民族主義を重視していたからに他ならないと私は考えています。したがってこの第一期から第二期に向かう先ほど述べた郷党的村的集まりから民族戦線へという変化は、人民党の方針の変化という形でおさえるべきはではなく、もっと重層的なプロセスです。
そしてだからこそ、島ぐるみ闘争の後におこった人民党と社会大衆党の対立は、たんに政党間の連携の分裂ということではなく、この努力の総体としての民族主義の消滅、すなわち利害の前提を変えていくことを放棄していく展開として、国場さんにはうつったのではないでしょうか。人民党が日本共産党の系列におかれ、同時に社会大衆党と対立していくプロセスは、たんに政党間の連携や対立、また政党の系列化ということだけで片付けられる問題ではなく、再構成され続ける民族主義の消滅であり、既存の秩序の中で区分された集団を、重ね合わせていくという努力の放棄であり、「沖縄の党」の消滅だったのではないでしょうか。それは、国場さんにとっては決して受け入れることのできない事態だったと思います。それが第三期の問題です。
ところで国場さんは、この第三期を、通貨のドルへの切り替えにおいて区分しています。したがいまして、通貨ということを画期にしている第三期の展開を考えるには、これまで述べてきた民族主義の再構成という問題に、資本という論点を重ねて検討しなければなりません。またそこにこそ国場さんのこの二つの論文の、今日においても決して色あせない力があります。最初の第一期の独立論のところでものべましたように、国場さんにとっては資本主義と対峙していくということは、沖縄解放において極めて重要な軸であり、民族主義をこの資本との対峙の中でどのように再構成するのかということが大切でした。そしてこうした論点においても、国場さんにとって「島ぐるみ闘争」の後の人民党の展開は、決して受けいれられるものではなかったと思います。論文においては直接的な人民党批判はなされていません。しかし、日本の左翼政党の綱領をそのまま受け入れることへの批判は、文章の中で何度も何度もくりかえし登場します。すなわち民族の再構成と資本への対峙をどう重ねるのかということが、重大な問題としてせりあがってくる状況であるにもかかわらず、後者の資本との対峙を日本の左翼政党の方針受け入れの問題にしてしまうことは、同時に前者の民族という領域を、自然化された素朴な一体感として放置することでもあったわけです。日本共産党との関係を強化するという一見左翼的展開に見える動きは、革命の放棄と民族の自然化、すなわち素朴な日本主義に民族主義が落ちって行く事態として国場さんには見えたのではないでしょうか。階級闘争の系列化と素朴な日本主義への回帰、あえていえばこの第三期の人民党の展開は、国場さんにとっては郷党的で村的な閉じた共同体としての民族主義に回帰していくプロセスにみえたのではないでしょうか。またそれは、まさしくこの時期に突き付けられた資本という問題を手放すこととしてありました。
ところで第三期の画期として指摘されている通貨切り替えの意味を考えるには、一つ目の論文「沖縄とアメリカ帝国主義―経済政策を中心に」が極めて重要です。また先取りしていえばそこで展開されているのは、今日の状況まで見通せる国場さんの沖縄にかかわる深い現状分析です。
この一つ目の論文で展開されているのは、第三期における米国の沖縄統治の転換ですが、それは同時に戦後における米国支配の本質にかかわる問題として見いだされています。この論文が書かれたのが1962年で、国場さんが第三期の画期と位置付けた1958年の通貨の切り替えからまだ三年しかたっていません。したがいまして、ここで国場さんが見出した第三期の沖縄統治の内実が、すぐさま今日にまで続く沖縄支配の本質という訳では到底あり得ません。それは当然のことでしょう。ですが、にもかかわらず、国場さんがたった三年のあいだに見出した沖縄統治の本質は、今日においても極めて重要な諸点を提示しています。またあらかじめ指摘すべきは、ここで国場さんが沖縄統治の問題として指摘しているのは、米国だけのことではありません。国場さんの表現をそのまま引用すれば、沖縄の統治は、「米日両帝国主義が反共軍事同盟の強化を背景として、アジアの諸国に対する一種の植民地主義を推進する政策」としてあります。またその際、国場さんが重視するのは、グローバルなミリタリズムの展開の中で自由に使える軍事基地というだけではなく、沖縄にかかわる日米両帝国主義の資本の動向です。少し具体的に見ていきたいと思います。
まず論文ではこうした第三期の展開の前史として、第二期の島ぐるみ闘争の時における経済分析がなされています。そこでは、人口拡大と基地にかかわる収入の限界の中で、生活が困窮し、いわゆる基地経済を軸とした沖縄経済が限界にきていることが指摘されています。さらにいえば、国場さんにとって「島ぐるみ闘争」は、単に土地問題というだけではなく、こうした基地経済の限界を契機にしているということでもあるでしょう。だからこそ第三期の展開において、その運動の契機である基盤が変化したということを、新たな解放闘争の構築として考える必要があったという訳です。ではどのように変化したのでしょうか。
注目すべきは、本質的には重なる二つの点です。一つは先ほどから述べているドルへの通貨切り替えであり、今一つは軍用地料の大幅引き上げです。まず前者の切り替えの意味は、金融資本の形成という点にあります。つまりそれは、琉球銀行に加え沖縄銀行の設立(1956)、復興金融基金の琉球開発金融公社への移行(1959)、また米国からのバンクオブアメリカの侵出という金融資本の形成を、ドル通貨への切り替えに重ね合わせているのです。またこうした動きと対応して、伊藤忠商事、三菱商事、三井物産といった商業資本が沖縄に侵出してきます。すなわちドルへの切り替えによる貨幣量の拡大が、金融と商業の資本形成を急激に促す事態として第三期があったわけです。もちろん生産業としては、パイン工場や製糖工場が投資先にはなっているのですが、重要なのは生産業より金融資本であり商業資本が軸になるという点です。いいかえれば生産業がつぶれようが、金融資本はまた別の投資先、例えば観光や大型開発事業にむかえばいいのであり、やや乱暴にいえば、農業も含めた生産業においては先が見えないにもかかわらず、なんとなく金が回っているというゆるやかなバブルのような経済が継続する構造が、ここにできあがったわけです。
また軍用地料の引き上げも、国場さんはこの金融資本の形成の文脈において理解しています。すなわち1959年の新たな軍用地料の算定水準は、例えば来間泰男さんのいいかたを借りれば、戦前日本の寄生地主制の高額小作料のような高額地代になります。そしてこうした地代が銀行を介して金融資本に転化していくのだと、国場さんは分析しました。
このように第三期において米国の統治は、金融資本を軸に再編されました。またこうした統治の軸である金融資本は電力や水道といった公的部門にもむかい、いわば日常生活にかかわる公的部門を買い取る形で投資が行われていきます。国場さんの表現をそのまま引用すれば、米国と米軍は「金融機関やエネルギー源など、沖縄経済の中枢部分を直接管理下におくことによって、沖縄経済全体を管理できる体制を築いた」、というわけです。
このような支配を表現するのに、単に植民地政策というだけでは、言葉が足りません。国場さんは何度も米国の統治は超過利潤を獲得する「古典的な意味での植民地政策ではない」と述べています。また同時に、戦後展開した生産分業と貿易を軸にした不等価交換による新植民地主義とよばれる事態とも違うと述べています。ではこのようなグローバルなミリタリズムの展開と金融資本による生活にかかわる公的領域までも支配するやりかたを、いったいどう呼べばいいのでしょうか。多分一番近いいい方は、グローバルミリタリズムと金融資本を軸とした新自由主義による統治ということになるかもしれません。事実国場さんは、この論文で自由貿易と自由貿易地区の設定に対し最大限の警戒を表明しています。またそこでは、日本からの資本流入も念頭に置かれているのであり、国場さんはこうした動きを「最近とみに自立的傾向と帝国主義復活の傾向を強めて来た日本独占資本」と述べています。いずれにしても第三期は、日米両帝国主義が沖縄において全面的に顔を出す時期といってもいいでしょう。
そしてなによりもこのような統治の構造は、1972年で消滅したわけではなく、沖縄は依然として自由に使える軍事基地でありつづけ、同時に金融資本による展開がその後も続くことになります。また金融資本が軸である以上、基本的には大型観光開発やそれに便乗した回収しやすい土木事業に投資が向かう訳ですから、自然環境はどんどん破壊されていきます。
また沖縄戦から継続する占領ということを考えると、一切を破壊した後、立法的統治や民主主義的制度ではなく、軍事的支配を根幹におく日常的な戒厳令状態に人々をおきながら、他方で生活領域までも市場化し金融資本に包摂していくという展開は、今日も世界各地で展開する支配形態かもしれません。ナオミ・クラインというカナダのジャーナリストはこうした世界に蔓延する支配を「ショック・ドクトリン」という言い方で説明し、そこでの資本のありかたを災害便乗型資本主義と述べています。それは、2001年の911以降におきた戦争と支配の問題でもあり、あるいは東日本大震災以降の日本の問題でもあるでしょう。そして今私は、国場さんの論文を読みながら、国場さんは今日世界各地で生じている軍事と資本主義のあり方を、1962年の時点ですでに沖縄に見出していたのではないかとさえ思います。このあたりはこれからゆっくり考えたいところです。
ともあれ、国場さんにおいては、第三期は極めて大きな転換期でした。そしてだからこそ資本の動きに対応した民族主義の再構成の必要性を押し出そうとしたのです。それがどのようなものであったのかは、論文からは明確にはわかりません。しかしながら想像すべきは、金融資本による新自由主義的展開の中で、総じて不安低層にならざるを得ない圧倒的な人々を「沖縄の党」が繋いでいくような展開を、国場さんは考えていたのではないでしょうか。それはたんに階層区分や利害集団のことではありません。階層横断的に総じて不安定にならざる負えない潜在的可能性を発見し、連結させていく努力の総体としての民族主義のありかたです。又だとするならば、先ほども述べたように資本の問題を本土の左派の綱領や方針におきかえ、民族主義を日の丸と血のつながりによるただの一体感に棚上げしてしまった人民党の展開を、国場さんが到底受け入れられないのは、容易に想像できます。
そう考えた時、国場さんが抱え込んでいた水脈、すなわち林義巳さんの奄美の党とともに非合法共産党を担い、ストライキを闘い、「島ぐるみ闘争」を組織していった水脈は、人民党をはじめとする政党とは質的に全く異なるものであったことがわかります。くりかえしますがそれは、既存の集団や利害を代表する政党ではなく、既存の集団から別の展開を引き出し、新たな関係性と集団性を模索し続ける党です。集団を代表するのではなく、集団の前提自体を問う作業を担う存在こそ、国場さんがいう「沖縄の党」に他ならないのではないでしょうか。そしてそれは民族主義でもあり、自治でもあり、島ぐるみの島でもあり、オール沖縄とも無関係ではないでしょう。そしてこのような国場さんの水脈を、今の状況の中でどう引き継ぐのかということが、この二つの論文を読む際の重要な論点であると私は考えます。
以上です。ありがとうございました。