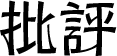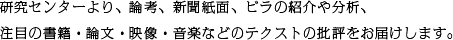【書評】「私は誰なのか」を問うやつら――冨山一郎『流着の思想』(ハングル版)
『ハンギョレ新聞』コラム「鄭喜鎮のあるメモ」
2015年3月28日(土)
冨山一郎『流着の思想』(沈正明訳)、2015
難しい文章は存在しない、ただ慣れていない思惟があるだけだという主張が正しいならば、バトラーと冨山一郎はかかる文章の代表的な筆者であろう。二人の文章の共通点は息詰まりそうな具体性と党派性。とりわけ、冨山の文章は、行と行のあいだが連結されていない。文章と文章のあいだは運動する。彼の身体は「流」と「着」を繰り返しながら進められていくのだ。過程としての文章書き。言葉が実践となる現場がそこにある。
彼の『戦場の記憶』『暴力の予感』につづいて『流着の思想』が刊行された。この本も同じく具体性から与えられる密度は圧巻だ。植民地の人間としての「私」の意味を考察する第3章は魯迅からはじまる(116頁)。魯迅は1926年の3・18事件の日に、「墨で書かれた虚言は、血で書かれた事実を隠すことはできない」、「血債はかならず同一物で返済されなければならない」と語った。
また、二年後には、「文章は所詮、墨で書くものだ。血で書かれたものは、血痕にしかすぎない。無論、それは文章よりもっと感動的であり、もっと直截的ではあろうけれども、しかし色が変わりやすく、消えやすい」と述べた。ここで「血」と「墨」はアレゴリーでは、ない。文字通りの意味だ。現実は言葉で構成され、実体を実体として成り立たせるのも言葉である。
私は誰なのか。すべての人間がこのように疑うのではない。この問いは、私の経験と社会の視線が一致しないとき、他人が勝手に私を定義するとき湧き上がるものである。私が誰なのかを悩むしかない状況は、「あなたは何者か」という尋問に対する一次的な反応である。
植民者は被植民者に「私は誰なのか」を自ら想起するように繰り返し追い込む(124頁)。またこの問いは、全面的暴力の始まりでもある。誰にでも生の特定の時期にこのような問いが求められる瞬間がある。ある人々は一生そのような質問に取り組まなければならない。「私は誰なのか」とは「あなたは何者か」からくるのであり、それは「問う私は人間だが、あなたは何者?」という暴力を前提に行われている。
著者が一貫して問題にするのは、かかる状況が被抑圧者の生に覆いかぶせている尋問の政治である。「女」、「アジュンマ」(訳注:結婚した女性を指すときもあるが、「女子力」を失ったという意味合いから女でも男でもない「第3階級」と呼ばれたり、年をとった女性に対する蔑称として通用されたりもする)、被植民者は二重メッセージ的状態におかれ、常に説明しろという要求に晒される。
だが、この地点こそが重要である。冨山の問いは、決して、正しい答に差し向けられているわけでは、ない。彼は、抑圧的状況に置かれている者たちがとるようになる身構えから「新たな人間」の可能性を探ろうとする。
故郷とは動き続ける自我の別名。流着とは二つの地域の移動を意味するのではない。二つの地域という前提はない。どこに行くのかということではなく、流れる、すなわち出郷することが重要なのである。出郷の先には帰りつくことのできない故郷が浮びあがる。故郷は離脱において登場し、想像上の未来において再登場するのだ(88~95頁)。
「私は誰なのか」という問いを強要するやつらにいかにして抗うか。身構えつつ、何を確保していくのか。最も容易な答、しかし不可能に近いのは、「本当の自分探し」であろう。これは既存の知識体系に「私たち」を縛っておくことをとおして、現実を固着させようとする植民者の論理に付き従って応え、「やつらの系統」を強化させる。相手が既に私を定義する権力を握っている、この束縛状態で如何なる言葉が可能なのか。
また魯迅に戻ってみよう。彼が「血」と「墨」を通して語ろうとしたのは何だろう。彼は身体を信じた。「墨」とは変身であり、変態した身体であろう。「血」とは私ではない。血が溜まった状態の体などはないのだ。語りまた書くという行為、つまり「墨」が身体なのである。実践過程のなかで変化する体。「墨」の可能性は未来を、「変わる可能性のある現在」(a transformative present)を作ることができる。冨山は流着というテーマをとおしてかかる現在の言葉にすべてを賭ける。
流着とは、ヒットエンドランではなかろうか。打ってはすぐに引きあげるということ。脱走、あるいは奪走。定住はいつも流れ着いた結果であり、再び流れ出すかもしれない予感に満ちている(90頁)。
(訳:ゆじん)
http://www.hani.co.kr/arti/