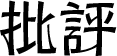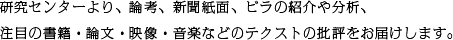【コラム】藤井たけし(ハンギョレ新聞コラム)「「現在」を問うということ」
한겨레신문 2014년6월29일 칼럼<세상읽기>
ハンギョレ新聞 2014年6月29日 コラム<風を読む>
藤井たけし、「「現在」を問うということ」

藤井たけし(歴史問題研究所研究室長)
最近話題になっている『帝国の慰安婦』 をやっと読むようになった。いろんな感じがしたが、最も重要な問題として感じられたのは、「運動」をみる彼女の視点であった。
「日本の支援運動」が「政治化」され、「帝国日本」のみではなく、「現代日本」まで批判することになったという指摘とともに、著者はつぎのように述べる。「慰安婦問題の解決が難しかったのは、まさにそのように、運動が「現在」を問う運動になったからでもある」。まるで壁にぶつかったような感覚だった。
1990年代日本で私が「慰安婦問題」解決のための運動に参加することになった理由が、まさに、それが現在を問う運動だと考えたからである。もちろん、「日本軍慰安婦」という存在自体は過去に属するのだが、問題としての「慰安婦問題」は現在の問題である。
また現在という時間のなかで、私もこの問題を知るようになった。すなわち、私は現在という時間を媒介にして慰安婦問題に出会ったのである。著者が過去と現在を分離する所以は帝国日本と戦後の日本の断絶を強調する立場からであるように見える。だがしかし、この問題を過去の問題だけで扱うとき、この媒介としての現在、いいかえれば「私たち」を可能にする現在は消えてしまう。残されるのは、専門家によって真実が究明されるべく過去の問題としての「慰安婦」のみである。
このように過去と現在の分離を裏付けるロジックは「当事者」と「支援者」という二分法である。著者は「結局、支援者たちの意図がなかったとしても慰安婦問題支援運動は問題の解決自体より、「日本社会の改革」という左派理念を重視することになった。そこでも、「慰安婦」は「当事者」にはなれなかったのである」というふうに、当事者性の問題を提起する。
かかる評価は国民基金が正解であったという前提から出されたものであるがゆえに、その妥当性にも問題があるが、より大きな問題は「慰安婦問題」を「慰安婦当事者」だけの問題として局限させようとする彼女の視線である。
「当時、支援者また支援団体が天皇制廃止のための「日本社会改革」への志向より慰安婦問題のみに集中したとしたら、慰安婦問題の解決は可能になったかもしれない」という評価はそうした視線を表している。結局のところ、純粋な支援運動ではなかったため、失敗したというのである。
このような論法の問題性は、今日韓国社会の文脈の中から考えてみると、さらに明らかになる。4・16(セウォル号惨事)以降から現在に至るまで継続している大規模の集会を非難するとき、よく使用されるのは「セウォル号事件を政治的に利用するな」という言い方である。
「朴グンへ政権退陣」というスローガンをかかげたり、チョンワデ(靑瓦臺)にむけて抗議したりする人々を「純粋な追悼でなく他の意図」をもつ存在として描き、かれらを分離させようとする試みは言論をとおして繰り返されている。にもかかわらず、多くの人々が街頭に立つのはかれらが「当事者」であるからである。
1990年代より慰安婦問題解決のために展開された運動の当事者も「慰安婦ハルモニ」だけでは、ない。当事者と支援者という二分法は、運動過程のなかで形成される「私たち」を崩し再びそれぞれの位置を固定させる。またそのプロセスのなかで、当事者は運動の成果を判定する基準となり、支援者はこの成果のために奉事する存在となる。ここでは、新たな社会は生成しない。
『帝国の慰安婦』には重要な省察も含まれている。慰安婦問題をとおして基地問題を思惟し、また資本の問題を提起する観点は大切である。にもかかわらず、結論では、「慰安婦問題をほんとうに解決したいとするならば、基地問題を解決しなければならないし、そのためにも日本との和解は必要である」と述べている。 米軍基地問題を解決するために日本と和解しようという不思議な主張が提示されるこの乖離は何なのか。
彼女はいかなる当事者なのか。
-ゆじん訳