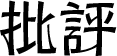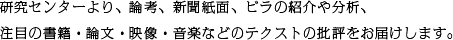自治という問いー書評鳥山淳『沖縄/基地社会の起源と相克 1945-1956』
自治という問い
書評鳥山淳『沖縄/基地社会の起源と相克 1945-1956』(勁草書房 2013年)
“Readings from Asia” section of the December 2015に掲載
冨山一郎
新聞を中心とした膨大な資料収集から生まれた同書より浮かび上がるのは、しかし、しばしば同書に対して語られるような実証性の深化ということではない。少なくともそれだけではない。同書の魅力は、膨大な資料をもとに慎重に語る歴史研究者による手堅い研究というよりも、未だいいあらわすことの出来ない領域を抱え込みながら、言葉の海を彷徨し続ける寄る辺のない単独者の軌跡にある。私が、同書を含めたこれまでの鳥山の仕事に魅かれるのは、この軌跡だ。またこの軌跡においてこそ、逆に沖縄近現代史とは何か、またさらにその歴史性にかかわって政治とは何か、さらに資料とは何かといういわば実証的歴史研究の前提に対する問いが、示されていくのである。
したがって同書を手堅い実証研究として読むか、単独者の軌跡として読むかということは、読みかかわる二つの選択肢というよりも、前者に対して後者は根底的な批判としてあり、同書を読むということにかけられた問いは、後者の軌跡が、広く共有されている前者の歴史記述への問いとして浮かび上がるかどうかという問題なのだ。私は、同書が示す歴史的事実の歴史学的意義の確認ではなく、同書が抱え持つこうした問いとして同書を評してみたい。そしてそれは、鳥山自身に突きつけたい問いでもある。私が同書に注釈を加えることにより、彼がなそうとしていることを単独者の軌跡として浮かび上がらせ、それが彼自身に対する問いとして構成されていく。こうした作業を行いたいと思うのだ。
本書で取り上げている1945年から1956年は、いわゆる沖縄戦後史の始まりにあたる。すなわち、1956年のプライス勧告と暴力的な土地収用に対する島ぐるみ闘争が、その後の復帰運動へと大きく動き出す時期なのだ。そして乱暴にいえばこの時期は、その後の復帰運動の起源を探ろうとする研究者のまなざしにさらされてきた。だが鳥山はこうした復帰運動史あるいは沖縄闘争史からさかのぼるのではなく、むしろこうした歴史化に抗する歴史を同時期に見出す。あえていえば、別の始まりがこの時期に抱え込まれているのだ。
鳥山がまず眼にすえるのは、戦場と化した郷土の中で難民化した人びとであり、戦場の中でその人びとが開始する生き延びようとする営みと「基地の島」としての沖縄の登場である。そしてこうした「固定化されていく米軍基地の傍らで生存の道を探り出さなければならなかった人々の姿」(41頁)に、戦後の始まりがあるのだ。それは同時に「基地に阻まれる帰郷」(28頁)を抱え込みながら生きることあり、いわば戦場をさまよう難民としての戦後なのだ。軍事的暴力の継続と、その中で戦後を生きようとする難民たち。ここに「基地の傍らで語られる『現実』」(155頁)が構成されていく。
この括弧が付けられた「現実」は、動かし難い歴史の基盤や事実的根拠を意味しているのではなく、いまだ終わらない戦場を戦後として生き延びるという行為において構成され続ける「現実」である。またそれが、決して安定的に整理されることのない力学系であり、いつ破綻するかもしれない危機を抱え込んだものであることは、容易に想像がつくだろう。沖縄の戦後は、いわば生き延びようとする強烈な希求を無理に押しとおす形で始まったのだ。そしてこの生き延びようとする営みは、先ほど述べたように、基地建設に関わる暴力的な土地収用において一つのクライマックスを迎える。それは、「基地の傍ら」の「現実」の中で構築された米国との協力関係において現状の打開を図っていた政治が、完全に破綻していくプロセスであり、この破綻を契機として政治は、日本への帰属を求める復帰運動へと流れ込んでいく。だからこそ多くの場合この時期を、占領への協力の終焉と抵抗の始まりという展開において議論しようとするのだ。
だがしかし、「基地の傍ら」の「現実」を注視する鳥山の作業は、協力から抵抗としての復帰運動へという展開を描くことではない。同書は、「協力と抵抗の二極に人々を振り分けようとする思考から距離を置きつつ、自治と復興の希求において何が問われ、何が賭けられていたのかを明らかにする」(9頁)のだ。この冒頭に記されている問題意識は、たんなる分析視角というよりも、基地の傍らで生存の道を探る人々を注視し続ける鳥山の、圧倒的な立場表明である。「距離をおく」という鳥山の慎重な言い回しをあえてシンプルに言い換えれば、復帰運動史あるいは沖縄闘争史ではないと彼は宣言しているのだ。
そしてこの彼の静かな決意を受け止めることができるかどうかということこそが、同書の読みに深くかかわる要点である。なぜならこの「協力と抵抗」から「自治と復興」への視点の移動は、AからBという移動ではく、後者のBがAへの根源的な批判としてあるからだ。基地の傍らの「現実」において、何を協力といい、何を抵抗というのか。あるいは「現実」を注視することなく、それを占領の悲惨さにおいて一様に塗りつぶしたうえで協力と抵抗の振り分けを行っているのは、いかなる制度であり学知なのか。そしてさらに、歴史研究自身がこの振り分けの張本人であるということが、この鳥山の立場表明の言外にはこめられているのである。だからこそ、同書は手堅い歴史書として読まれるべきではないのだ。
たとえば鳥山が「『米琉親善』にまとわりつくいらだち」(158頁)あるいは「強いられた協力とともに折り重なってきたいらだち」(245頁)と述べるとき、彼がこの「いらだち」という歴史分析にはふさわしくない言葉において何を確保しようとしているのかが、まずは了解されなければならないだろう。すなわち協力を「強いられた協力」として受け止め続ける者の身体に蓄えられる「いらだち」は、同時にまちがいなく協力を破棄する身構えでもある。そこでは協力は協力に収まらない外部を「いらだち」として不断に抱え込むのであり、あえていえば協力は同時に抵抗の身構えでもあるのだ。そしてかかる身構えは、協力と抵抗を区分けした瞬間に消失する。だからこそ重要なのは、この両者の区分ではなく、つながりのプロセスを確保することであり、それこそが復興を担う自治にかかわる問いである。また鳥山は後段で、「占領に抗する主体」という言葉を用いている。そこにあえて注釈をくわえればそれは、協力から区分された抵抗をくくり出した主体ではない。それは基地の傍らで生まれる難民たちの主体性であり、その主体は、区分を担う範疇概念や名詞において語られるものではなく、プロセスという時間において確保されるのだ。
ここに自治が問いとして浮かび上がる。鳥山は自治と復興がこの生の近傍にあることを発見したのである。そこでは何が自治かという範疇的問いではなく、プロセスとしてそれをどう確保するのかという主体にかかわる問いこそが重要なる。確かに戦後沖縄史の研究は、復帰運動にしろ沖縄闘争にしろ、抵抗を軸に描かれている。そこにはどこまでも抵抗運動を発見したいと思う歴史研究を担う者たちの勝手な欲望が間違いなくあるだろう。そして基地の傍らで生き延びようとする生は、この欲望において区分けされ、区分けされることにより身構える者たちが担うプロセスは消去される。鳥山が凝視しようとするのは、抵抗を定義するその欲望の機制それ自体が、難民たちの生において拒絶されているのではないかという問いであり、こうした問いなくして抵抗もまた語ることは出来ないということを問題意識として宣言しているのだ。
しかしそれは一般命題ではなく、沖縄近現代史それ自体に深く関わっている問いに他ならない。沖縄は近現代を通して、いわゆる主権において構成される法制度の例外状態におかれつづけてきた。あるいは例外化するぞという恫喝を受け続けたともいえる。いわば、法が停止し、問答無用の暴力が秩序を担いはじめる戒厳状態が、いつも準備されまた実現している場所なのだ。沖縄の戦後を定義づける「潜在主権」は、このことを端的に示している。また1972年以降においても密約あるいは特別措置法などにおいて、不断に例外化され続けている。かかる無法な戒厳状態は占領あるいは植民地主義でもあるかもしれない。
しかし今こうした例外状態をどう呼ぶかが、問題なのではない。重要なのは、主権を前提にした政治領域が制度的に剥奪された戒厳状態において発話される言葉を、どう受け止めるのかという問いを抜きにして、沖縄の政治は語れないということだ。言葉が停止し暴力が状況を支配する中で、何を政治と呼び、いかなる言葉を政治にかかわる言葉とみなすのか。多くの場合こうしたことは問われることのない前提とされた上で政治が語られ、また考察される。しかし こうした問いを立てないまま描き出される政治は、それ自体沖縄が抱え込んだ領域、すなわち基地の傍らにある生の削除になる。あえていえば政治は右や左、保守や革新の力学において構成されるのではないのだ。
こうしたことを踏まえながら、再度鳥山のいう「強いられた協力」を考えてみよう。この協力は、協力関係の制度的保証がないことを前提にしている。共に協力するステージなど存在しないのだ。だからこそ協力は、協力という政治領域が存在しないにもかかわらず協力を演じ続ける協力なのである。あるいは協力は、同時に協力が成り立たないことを確認していく作業でもある。したがってこの協力とは、協力を成り立たせる未来の制度化と制度を先取りした主張が合体した言葉なのだ。いいかえれば制度を前提にした言葉は、ベンヤミンにならっていえば、制度を構成する法措定的な暴力とともにある。またこうした制度と制度外の力が同時に重なり合うある種の遂行的意味は、法が停止する戒厳状態における発話を考える上で極めて重要である。すなわちその重なりは、戒厳状態という状況において登場するものであり、歴史学の作法としてなされる主体の意図やその属性において定義されるものではない。そこには、言葉を既存の個人や集団に区分けして定義し、解釈を施す歴史学への、根本的な批判があるだろう。またこうした同書の問題意識は、鳥山自身による歴史学的記述への批判となって跳ね返るだろう。それはとりわけ以下に述べる民族あるいは独立ということばにかかわっている。結論を先取りすれば、この言葉にこそ、鳥山の重視する自治の決して範疇的には振り分けることのできないプロセスが囲い込まれているのだが、鳥山は自治と民族あるいは独立を慎重に区分けしようとしているように思える。
本書が扱う時期においては、沖縄民族あるいは琉球民族という言葉が頻繁に登場する。あるいは独立ということも語られた。民族や独立は仲宗根源和らの沖縄民主同盟の独立論や沖縄人民党の沖縄民族解放のみならず、沖縄戦における住民虐殺の記憶が想起される中でも語り出されている。まず民族から考えよう。このような民族は、人類学者が命名する均質な同一性を意味するカテゴリーではない。元来民族は自称としてあり、そこには複数の歴史経験から集団性を構成しようとする強い目的性がある。ファノンならっていえば「努力の総体」なのであり、複数の様々な力の合力なのだ。それはまた制度を越えた力でもある。
難民化した人々、さらには当該期に基地建設にかかわって奄美から流入する大量の人々をまえにして、いかなる「努力の総体」がなされるのか。民族とは、まさしくこうした流民の集団性を構成する努力としてあった。そしてこうした努力は、やはり自治という問題に深くかかわるのではないか。しかし党派政治を越えた民族という集団性の可能性については、本書では慎重に議論が回避されているように思える。だが占領状態において自治とは、がんらい強いられた自治なのであり、自治制度と同時に自治制度を越える法措定的な暴力がそこでは重なり合っている。自治は自治としてのみ語られることはなく、それはやはり民族あるいは独立という問題と深くかかわるだろう。
「我々は独立するんだとの意気でいきたい」とのべ、「沖縄はただ沖縄人に属するだけである」という仲宗根源和の言葉に対して、「ただし、復興の課題とともに掲げられる『我々』をすぐさま『独立』への志向として捉えることは、慎重に避けなければならない。それは何らかの帰属形態に縛られたものではなく、より根源的な願望を背負った主体性として理解されるべきものであるに違いない」と鳥山が注釈を加える時(81頁)、独立にかかわる言葉を帰属問題へと還元しているのは鳥山自身のように思える。重要なのは、独立か主体性かという分析者の範疇区分ではない。また独立が単に仲宗根源和の政治的意図や沖縄民主同盟の方針ということでもない。占領状態においては、自治と独立が一体のプロセスとして存在しているということ自体が重要なのだ。鳥山自身が、「日本の帰属に自治の実現を賭けようとする地点から、日本復帰運動は開始された」(142頁)と述べていることと同様に、独立にも自治が賭けられているのであり、独立運動において自治が語りうるのだ。いいかえれば独立をすぐさま帰属問題にしてしまうこと自体が、そこにある多くの可能性を見失う結果になるのではないか。
それは鶴見俊輔が民主主義という制度を考える時、制度自体を越えた革命を考えていなければならないと述べたことでもあるかもしれない(鶴見俊輔「革命について」『思想の科学』1963年4月)。すなわち、革命を志向する志のないところでは民主主義もないと鶴見は述べる。民主主義は制度をなぞることでも、守ることでもなく、革命という制度を越えた力とともにあるのだ。鶴見にとって民主主義は、沖縄の自治と同様、制度として保証されている訳ではない。民主主義を語ることは制度を語ることであると同時に制度を越えた革命を語ることなのだ。制度的保障がない中で語られる自治制度もまた、制度外の法措定的な暴力と共においてこそ語りうる。そして制度と制度外は範疇的に区分けできるものではない。重要なのは主権一般の是非でもなければ国家への帰属問題でもなく、独立という言葉においてこそ自治が語りうるという両者のプロセスとしての重なりであり、この重なりの中にこそ主体という問いが生まれるのではないか。
問答無用の新たな基地建設に対して、今もまた沖縄においては、強いられた自治を語る者たちの身体に蓄えられていった「いらだち」が、身構えとして登場しつつある。それは自治を独立として語らなければならない戒厳状態を意味していると同時に、この独立に賭けられた戒厳状態からの離脱こそ、既存の国家なるものを根源的に批判し続けることのできる起点を確保するのではないのだろうか。鶴見が革命に民主主義を重ね続けることにおいて、日々の日常生活の中に革命への志を確保しようとしたように、独立に自治を重ね続けることは、変わりうる現実を生き延びることなのであり、決してたんなる既存国家の帰属問題ではないのだ。