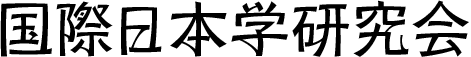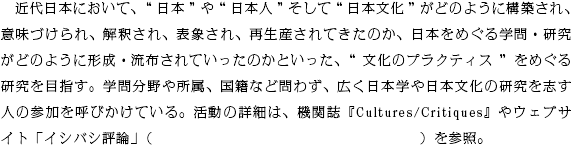8回目の会合を終えて
永岡 崇(事務局)
8月2日(土)、南山宗教文化研究所にて、国際日本学研究会の第8回学術大会を開催した。
コンセプトも、運営もかなりいい加減にやってきているというのが正直なところだが、とにかく手探りで「日本研究」なるものを実践している人びとが集まって議論する場を作りたいというのが、僕なりに理解している初志である。
とはいえ、いまのところ日本語での発表を求めたり、時代的に近世後期以降を対象としたものがほとんどだったり、と、うまく開くことができていない部分も多く、これからどうしていくべきなのか、議論を深めていく必要がある。
そのような限界を抱えながらも、今回は大学院生など若手研究者による8本の発表があり、民俗研究・映画研究・ジェンダー研究・キリスト教神学・植民地主義といった領域にわたる多様な議論が展開された。
発表者募集の段階から、なにか決まったテーマを設定したわけでもなく、漠然と「日本研究」というくくりを作っているだけなので(しかも「日本研究」とは何か、ということについても各々の解釈に任せている)、当然ながらテーマがバラバラになっていくわけなのだ。神学をやっている人は民俗学に疎いかもしれないし、逆もまたしかり。互いに使っていることばも違っているし、大切だと思っていることも異なっているだろう。だから「難しくて言ってることがよくわからない」と感じることもあるし、「そんなことを調べて意味あるんですか?」と思うこともある。
そのような戸惑いというのは「~学」といった既存の学問分野内の集まりでもつねに起こっていることだと思うのだが、当研究会ではその戸惑いを積極的に引き受けようとしているのだ、と考えたい。理念的にいえば、すべての参加者にとってアウェーであるような議論の場、ということになるだろうか。それでも他の人に自分の考えを伝えようとするなら、なにか喋り方を工夫する必要があるだろうし、聞く側にとっても聞き方の工夫が必要になり、その過程である種の「開かれ」が生じる可能性があると思われる。「ホーム」での作法が通用せず、「ホーム」では考える必要がないようなことについて考える場というか(その意味では、「日本研究」という縛りすら必要ないのではないか、という気もしてくるのだが、そうなると話し合い自体が成り立たないのだろうか?)。
もちろん、実際の国際日本学研究会の場でそのような出会いが可能になっているわけではなく、アウェーだと思う人もいれば、ホームだと思う人もいるというのが本当のところだと思う。ホーム/アウェーの二分法を脱構築して、歓待の場を生成させるにはどうしたらいいのか、今のところ僕にはよくわからないが、今回の参加者の議論を聞いていると、それが必ずしも非現実な理想ともいえないのではないか、という気がした。それぞれの人が他のそれぞれの発表に対しては門外漢だが、門外漢であることに居直るのではなく、「自分の知らないこと」への関心を持続させて活発な質疑が起こっていたところに、ある種の可能性を感じた次第である。可能性の中身を厳しく問い詰められても困るが、そこはじっくり考えさせていただきたい。
そういうわけで、今後ともよろしく。